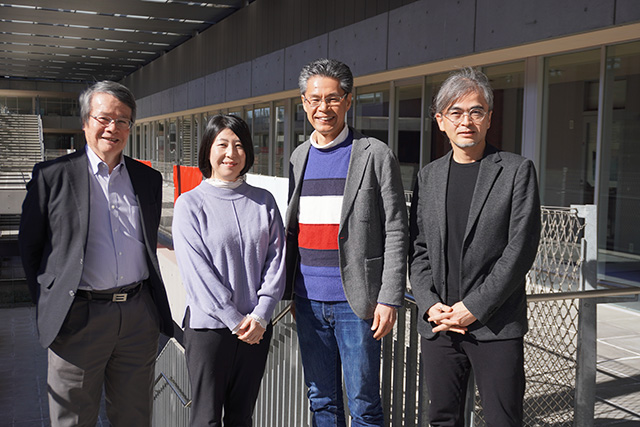
これからソーシャルイノベーションデザイナーの資格をどのように周知していこうと考えておられますか。
青山:認知度を高めるのはCOLPUの役割ではあるんですけど、我々としては大学が旗印になるとやりやすいと考えています。
中森:ソーシャルイノベーションデザイナーは、業務独占資格である医師や弁護士と違って、別に資格を持ってない人でも業務はできるんですよ。例えばコンサルタントもそうです。中小企業診断士という資格がありますが、この資格を持っていなくてもコンサルタントとしての業務ができます。業務独占資格でないものが認知されていくのはやっぱり成功モデルの積み重ねなんですよね。そう考えると、ソーシャルイノベーションデザイナーの資格を持った人が育って、いろんなところで活躍していくことが、一見して時間がかかるように思われますが、社会で認知されるためのいちばん早い方法であり、要素であると思います。
的場:その一方で、我々も企業と密にコミュニケーションを図り、こういう資格があります、こういう能力が発揮できます、といったことを積極的に広報していく必要もあると思っています。また、龍谷大学が関わっているソーシャル企業認証制度(S認証)の認証を受けている企業など、元々ソーシャルなことを考えている企業の方々と一緒に、企業側の人材ニーズを調査したり、研修プログラムの内容をブラッシュアップしたりすることも必要になってくると思います。
青山:私は名古屋のシンクタンク事務所に携わっているのですが、業務に役立つ資格を持っている人には手当を出しています。ソーシャルイノベーションデザイナーの資格も持っていると手当が出るようになると取る人も増えるし、認知度も高まるでしょうね。
中森:職場で資格手当が支払われるようになるには、企業にソーシャルイノベーションデザイナーの必要性をわかってもらうことも大切です。そのためにはソーシャル・イノベーションみたいなことに取り組んでいる企業と、そうでない企業の業績比較や社員のワークエンゲージメントの差などを分析し、何らかの効果があることを、アカデミックな視点から裏付けしていく必要があると考えています。それも継続的にやっていくことでより評価ができるように思います。ただしその指標を開発せねばなりません。だから、その効果をどうやったら測れるんだろう、今まで思ってなかったようなところにどんな効果が出ていて、それをどうやると見ることができるんだろう、といったことを考えるのは、我々研究者の役割です。今後、ある程度の人がこの資格を取得して、ある程度の事例がたまってきて、この指標を見たら確実に差が見られるというものを提示できるようになると、ソーシャルイノベーションデザイナーの有効性が評価しやすくなり、企業でも理解が進むのだと思います。

青山:これからは企業側も社会課題解決に対する意識を持たないといけない時代ですからね。すでにアメリカは環境に優しいとか、ソーシャルな活動をしているということがちゃんと指標化されて、投資家たちは指標が低いところには投資しないという流れになってきています。日本の企業はまだ遅れているので、ソーシャル・イノベーション的な発想を持った人材がどんどん企業に入り、社長やりましょうよっていうふうにしていかないといけません。
中森:ただ企業はどうしても便利な方へ、儲かる方へという経済合理的な発想になってしまいます。でも、これからは経済合理の追求でないところが非常に重要で、むしろ経済不合理なところで、どうやったらその不合理さを克服できるのかっていうことを考えていくことが大事になってきます。 短期的な経済合理性を追求すれば、経営に関する数字を計算して、コストの悪い事業部門を切る、生産性が上がらない部門の社員を削減する、労働コストを下げるために非正規雇用を増やすといったような、経済性の追求が目的となるでしょう。でも、SIを学ぶときは社会課題から入っていきます。 社会課題を解決することを目的にします。社会課題は何があるんだ、なぜその社会課題が生まれてきたのかっていう社会構造の根源のところから見ていって、どうやったら解決できるのか、それをどうやったら事業として続けられるのかを考えていく。短期的な経済合理性の追求とはまた違う方向を我々は目指している。 そこが実は面白いし、企業の方々にもわかってもらう必要があると思っています。
企業の意識を変えることがまず大切なのですね。そのためにはソーシャルイノベーションデザイナーの人たちが活発に活動することが大切だと思うのですが、ソーシャルイノベーションデザイナー資格取得者同士が、卒業後もつながりを深めていける場などはありますか。
中森:ソーシャルイノベーションデザイナーの人たちのネットワークを作るだけでなく、成功モデルの勉強会をするとか、あるいは社会課題を持ち寄って、相談料や必要な費用をいただきながら解決していけるような仕組みを作れたら、持続的なネットワークになるのではないかと考えています。
宮本:COLPUとしても、「地域公共政策士会」という地域公共政策士を取得している人たちの集まりのようなソーシャルイノベーションデザイナー版を作っていこうと思っています。そこで先ほど中森先生がおっしゃったような勉強会をやったり、ネットワークを広げたりしていただきたい。資格を持った人が積み重なっていくと面白いことになっていくと思います。
中森:本学の大石先生が責任者となって、2025年度の日本ソーシャル・イノベーション学会の定期大会が龍谷大学で開催されるとこが決まっているので、そこで院生に研究発表してもらうことも考えています。学会などでのつながりも将来的に重要なものとなると思います。
宮本:龍谷大学は資格への理解や取り組む姿勢が違いますよね。地域公共政策士の資格を運用するにあたり、そう感じています。

中森:自分事として捉えられているのか、制度だから仕方なくやるのかの違いみたいなものがあるのかもしれません。何かと向き合う(対峙する)ときも同じで、言われているから仕方なくやるよりも、自分事として主体的に取り組んだ方が、やっぱり工夫につながると思います。
これは我々サイドの話になりますけれど、資格を本格的に使えるものにするには、熟練世代だけでなく若い世代の人たちにも、理念や考え方などを継承しつつ自分ごととして工夫していってもらうっていうことも大事なんです。何でもそうですけど、立ち上げ期ってみんながやろうっていう感じなるけれど、続けていくことはやっぱり難しい。そして続けるためには変わらないといけないところもある。本当に続けるためにはどうしたらいいのかっていうことを、次の時代を担う人と一緒に、今から考えていかなければならないと思っています。
宮本:龍谷大学は先生同士も、事務の方もコミュニケーションをすごく密に取られて、誰もが最初の思いをずっと引き継がれているので安心です。私たちは今後、資格を取得できる大学を拡大していく上で、新しく入ってくる大学とも連携できるプログラムや、仕組みを作って土台を固め、長く続く資格にしていきたいと思っています。
ソーシャルイノベーションデザイナーはどんな立場の人でも役立つ資格だと感じました。文系の人だけでなく、理系の人も取得したほうが良いのでは思うのですがいかがでしょう。
青山:全くその通りです。このプログラムが始まったときに、ヨーロッパ各国の調査に行ったのですが、データサイエンスやITといった要素を必ず入れないと駄目だっていうことをしきりに言われました。 だから文系の科目だけでなく、情報などの要素を入れました。理系の人の発想もすごく重要なんですよ。実際、バイオプラスチックと廃棄物量で実現する環境に優しい製品作りとか、イグサを使って地域の一つの新しい製品をつくるとか、製造業が中心になってソーシャル・イノベーションの考えを入れて成功した事例はたくさんあります。理系の人と出会い、発想をうまく融合させることでイノベーションが起こる。何度も話に出てきましたが、3大学とも社会人の院生がたくさんいます。龍谷大学や琉球大学の専門も業種が違う人たちが一緒に集って何か話をしたりとか、議論したりできるうえ、そこに京都文教大学の臨床心理系という業界の違う人が入ってくるから、もっと面白いことが起こる。同じジャンルの人たちばかりだと、なかなか新しい発想は生まれにくいですから。
的場:どんな人が資格を取るにせよ、最終的には資格を持った本人たちが活躍しないと駄目です。ヨーロッパにはさまざまな職能資格があるんですが、それが機能している理由は、それぞれの資格取得者が活躍しているからなんですね。資格を取るために学んだことが役に立って、ちゃんとその企業に貢献できているから、社会にしっかりと根付いている。ソーシャルイノベーションデザイナーもそうなっていかなければならないので、我々としては企業に対し、この資格を持った人はこういう分野で活躍できますという情報を提示することが必要になってきますし、中森先生がおっしゃったみたいにソーシャル・イノベーションそのものについてもその価値をアカデミックなものにして見せていくこともしなければいけない。そうすることでソーシャルイノベーションデザイナーソーシャルイノベーションデザイナーが意味のある資格だということ示したいと考えています。
中森:人が共存しながら持続的に繁栄していくためには、人としてやるべきことは、やっぱり社会課題の解決だとか、人のお困りごとを考えるっていうことだと思うんです。ビジネスにしても、自分のところだけが大きな利益を効率よく得るだけではなくて、困っている人たちの役に立って、結果的にお金として入ってくることが大事だと思います。だからSIに進んでくる人たちには、そのことをまず考えてほしいと思っています。社会の様々な課題についてしっかり考え、ソーシャルイノベーションデザイナーとして社会を変えるような人になっていただきたいと思います。

育てる側、認める側がそれぞれ考える
ソーシャル・イノベーションを担う人材の証「ソーシャルイノベーションデザイナー」とは【後編】
[ 2025.3.31 更新 ]
これからソーシャルイノベーションデザイナーの資格をどのように周知していこうと考えておられますか。
青山:認知度を高めるのはCOLPUの役割ではあるんですけど、我々としては大学が旗印になるとやりやすいと考えています。
中森:ソーシャルイノベーションデザイナーは、業務独占資格である医師や弁護士と違って、別に資格を持ってない人でも業務はできるんですよ。例えばコンサルタントもそうです。中小企業診断士という資格がありますが、この資格を持っていなくてもコンサルタントとしての業務ができます。業務独占資格でないものが認知されていくのはやっぱり成功モデルの積み重ねなんですよね。そう考えると、ソーシャルイノベーションデザイナーの資格を持った人が育って、いろんなところで活躍していくことが、一見して時間がかかるように思われますが、社会で認知されるためのいちばん早い方法であり、要素であると思います。
的場:その一方で、我々も企業と密にコミュニケーションを図り、こういう資格があります、こういう能力が発揮できます、といったことを積極的に広報していく必要もあると思っています。また、龍谷大学が関わっているソーシャル企業認証制度(S認証)の認証を受けている企業など、元々ソーシャルなことを考えている企業の方々と一緒に、企業側の人材ニーズを調査したり、研修プログラムの内容をブラッシュアップしたりすることも必要になってくると思います。
青山:私は名古屋のシンクタンク事務所に携わっているのですが、業務に役立つ資格を持っている人には手当を出しています。ソーシャルイノベーションデザイナーの資格も持っていると手当が出るようになると取る人も増えるし、認知度も高まるでしょうね。
中森:職場で資格手当が支払われるようになるには、企業にソーシャルイノベーションデザイナーの必要性をわかってもらうことも大切です。そのためにはソーシャル・イノベーションみたいなことに取り組んでいる企業と、そうでない企業の業績比較や社員のワークエンゲージメントの差などを分析し、何らかの効果があることを、アカデミックな視点から裏付けしていく必要があると考えています。それも継続的にやっていくことでより評価ができるように思います。ただしその指標を開発せねばなりません。だから、その効果をどうやったら測れるんだろう、今まで思ってなかったようなところにどんな効果が出ていて、それをどうやると見ることができるんだろう、といったことを考えるのは、我々研究者の役割です。今後、ある程度の人がこの資格を取得して、ある程度の事例がたまってきて、この指標を見たら確実に差が見られるというものを提示できるようになると、ソーシャルイノベーションデザイナーの有効性が評価しやすくなり、企業でも理解が進むのだと思います。
青山:これからは企業側も社会課題解決に対する意識を持たないといけない時代ですからね。すでにアメリカは環境に優しいとか、ソーシャルな活動をしているということがちゃんと指標化されて、投資家たちは指標が低いところには投資しないという流れになってきています。日本の企業はまだ遅れているので、ソーシャル・イノベーション的な発想を持った人材がどんどん企業に入り、社長やりましょうよっていうふうにしていかないといけません。
中森:ただ企業はどうしても便利な方へ、儲かる方へという経済合理的な発想になってしまいます。でも、これからは経済合理の追求でないところが非常に重要で、むしろ経済不合理なところで、どうやったらその不合理さを克服できるのかっていうことを考えていくことが大事になってきます。 短期的な経済合理性を追求すれば、経営に関する数字を計算して、コストの悪い事業部門を切る、生産性が上がらない部門の社員を削減する、労働コストを下げるために非正規雇用を増やすといったような、経済性の追求が目的となるでしょう。でも、SIを学ぶときは社会課題から入っていきます。 社会課題を解決することを目的にします。社会課題は何があるんだ、なぜその社会課題が生まれてきたのかっていう社会構造の根源のところから見ていって、どうやったら解決できるのか、それをどうやったら事業として続けられるのかを考えていく。短期的な経済合理性の追求とはまた違う方向を我々は目指している。 そこが実は面白いし、企業の方々にもわかってもらう必要があると思っています。
企業の意識を変えることがまず大切なのですね。そのためにはソーシャルイノベーションデザイナーの人たちが活発に活動することが大切だと思うのですが、ソーシャルイノベーションデザイナー資格取得者同士が、卒業後もつながりを深めていける場などはありますか。
中森:ソーシャルイノベーションデザイナーの人たちのネットワークを作るだけでなく、成功モデルの勉強会をするとか、あるいは社会課題を持ち寄って、相談料や必要な費用をいただきながら解決していけるような仕組みを作れたら、持続的なネットワークになるのではないかと考えています。
宮本:COLPUとしても、「地域公共政策士会」という地域公共政策士を取得している人たちの集まりのようなソーシャルイノベーションデザイナー版を作っていこうと思っています。そこで先ほど中森先生がおっしゃったような勉強会をやったり、ネットワークを広げたりしていただきたい。資格を持った人が積み重なっていくと面白いことになっていくと思います。
中森:本学の大石先生が責任者となって、2025年度の日本ソーシャル・イノベーション学会の定期大会が龍谷大学で開催されるとこが決まっているので、そこで院生に研究発表してもらうことも考えています。学会などでのつながりも将来的に重要なものとなると思います。
宮本:龍谷大学は資格への理解や取り組む姿勢が違いますよね。地域公共政策士の資格を運用するにあたり、そう感じています。
中森:自分事として捉えられているのか、制度だから仕方なくやるのかの違いみたいなものがあるのかもしれません。何かと向き合う(対峙する)ときも同じで、言われているから仕方なくやるよりも、自分事として主体的に取り組んだ方が、やっぱり工夫につながると思います。
これは我々サイドの話になりますけれど、資格を本格的に使えるものにするには、熟練世代だけでなく若い世代の人たちにも、理念や考え方などを継承しつつ自分ごととして工夫していってもらうっていうことも大事なんです。何でもそうですけど、立ち上げ期ってみんながやろうっていう感じなるけれど、続けていくことはやっぱり難しい。そして続けるためには変わらないといけないところもある。本当に続けるためにはどうしたらいいのかっていうことを、次の時代を担う人と一緒に、今から考えていかなければならないと思っています。
宮本:龍谷大学は先生同士も、事務の方もコミュニケーションをすごく密に取られて、誰もが最初の思いをずっと引き継がれているので安心です。私たちは今後、資格を取得できる大学を拡大していく上で、新しく入ってくる大学とも連携できるプログラムや、仕組みを作って土台を固め、長く続く資格にしていきたいと思っています。
ソーシャルイノベーションデザイナーはどんな立場の人でも役立つ資格だと感じました。文系の人だけでなく、理系の人も取得したほうが良いのでは思うのですがいかがでしょう。
青山:全くその通りです。このプログラムが始まったときに、ヨーロッパ各国の調査に行ったのですが、データサイエンスやITといった要素を必ず入れないと駄目だっていうことをしきりに言われました。 だから文系の科目だけでなく、情報などの要素を入れました。理系の人の発想もすごく重要なんですよ。実際、バイオプラスチックと廃棄物量で実現する環境に優しい製品作りとか、イグサを使って地域の一つの新しい製品をつくるとか、製造業が中心になってソーシャル・イノベーションの考えを入れて成功した事例はたくさんあります。理系の人と出会い、発想をうまく融合させることでイノベーションが起こる。何度も話に出てきましたが、3大学とも社会人の院生がたくさんいます。龍谷大学や琉球大学の専門も業種が違う人たちが一緒に集って何か話をしたりとか、議論したりできるうえ、そこに京都文教大学の臨床心理系という業界の違う人が入ってくるから、もっと面白いことが起こる。同じジャンルの人たちばかりだと、なかなか新しい発想は生まれにくいですから。
的場:どんな人が資格を取るにせよ、最終的には資格を持った本人たちが活躍しないと駄目です。ヨーロッパにはさまざまな職能資格があるんですが、それが機能している理由は、それぞれの資格取得者が活躍しているからなんですね。資格を取るために学んだことが役に立って、ちゃんとその企業に貢献できているから、社会にしっかりと根付いている。ソーシャルイノベーションデザイナーもそうなっていかなければならないので、我々としては企業に対し、この資格を持った人はこういう分野で活躍できますという情報を提示することが必要になってきますし、中森先生がおっしゃったみたいにソーシャル・イノベーションそのものについてもその価値をアカデミックなものにして見せていくこともしなければいけない。そうすることでソーシャルイノベーションデザイナーソーシャルイノベーションデザイナーが意味のある資格だということ示したいと考えています。
中森:人が共存しながら持続的に繁栄していくためには、人としてやるべきことは、やっぱり社会課題の解決だとか、人のお困りごとを考えるっていうことだと思うんです。ビジネスにしても、自分のところだけが大きな利益を効率よく得るだけではなくて、困っている人たちの役に立って、結果的にお金として入ってくることが大事だと思います。だからSIに進んでくる人たちには、そのことをまず考えてほしいと思っています。社会の様々な課題についてしっかり考え、ソーシャルイノベーションデザイナーとして社会を変えるような人になっていただきたいと思います。