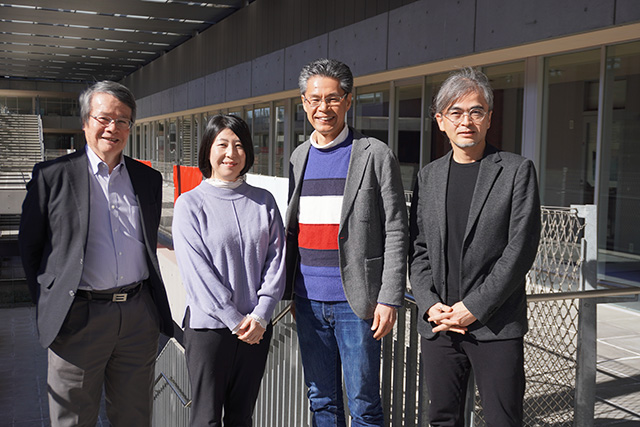
ソーシャルイノベーションデザイナーという資格名に込められた思いや地域公共政策士との違いを具体的に教えてください。
青山:最近、様々な分野でプランニングをする人たちのことをデザイナーと呼ぶことが多くなってきたことを受け、ソーシャルイノベーションデザイナーと名付けました。
的場:自分自身が事業をデザインするだけではなく、ソーシャル・イノベーションの考え方を理解した上で今いる環境で新たなしくみをデザインする、といった能力も視野に入れています。
中森:ソーシャルイノベーションデザイナーと地域公共政策士は似ているといえば似ていますが、違う側面から見たら全く違うんですよね。地域公共政策士は公共政策をプランニングする人たちですが、近年、社会の課題が複雑化したことによって、条例を作る、補助金を出すといったこれまでの公共政策では解決できなくなってきた。その一方で民間企業は企業の社会的責任が意識されてきて社会に対して貢献しようという意欲が高まってきている。その社会課題解決に対する動きを事業として展開することで、持続的に続いていくものとなると考えています。
青山:少し前になりますが、イギリスでソーシャルビジネスという言葉が生まれましたよね。困っている人たちを支援する仕事を、公務員をしていた人が外に出てビジネスとしてやりはじめ、そして行政も社会課題の解決をビジネスとして成り立たせているところを支援するようになった。これがアメリカにも広がり、今ではたくさんのノンプロフィットの組織が社会的な事業をやっています。
私としては、企業だけでなくまだボランティア的なイメージが強い日本のNPOも、ビジネス的な視点を入れていけるといいのではないかなと思っています。このプログラムの授業で学んでいただいたことを、ビジネスにしていきましょうよ、ということですね。例えば今、国が推進している農福連携もビジネスとしてやっていくことが重要だと思います。
的場:その通りです。私としては公共事業や政策づくりに関わっている公務員の方にも、取得してほしいと思っています。青山先生がおっしゃったイギリスの公務員のように外に出ていってビジネスをしなくても、ソーシャル・イノベーション的なマインドを持つ事業を理解してそれをサポートするような政策を打つとか、公務員だからこそ可能なソーシャル・イノベーションの取り組みも色々とあると思います。
中森:地域公共政策士は行政や政治家、NPOの人たちが対象、ソーシャルイノベーションデザイナーは民間企業の人たちが対象と言ったら、きっとわかりやすいと思います。しかし、的場先生がおっしゃるように行政の人たちもこれからは事業マインドや事業スキルが必要ですし、民間企業は利己的で儲からないことには一切参加しないとなると、社会課題の解決というような長期的な目線での物事の判断ができなくなります。ですから地域公共政策士を民間企業の方々も取れる、公共の人たちがソーシャルイノベーションデザイナーも取れるようにしています。
的場:地域公共政策士と、より革新的なイメージがあるソーシャルイノベーションデザイナーの両方が取れることは研究科としても強みになりますし、学び手としても魅力的だと思います。ソーシャルイノベーションデザイナーの資格を目指す民間企業にお勤めの方には、NPOや公務員、議員など違うセクターの人たちと同じ教室で学んで、ソーシャル・イノベーションについて多様な視点から大いに議論していただきたいですね。
中森:それぞれの出口が違っても、地域の社会課題の解決に向けて、どうやったら解決できるのだろうかということを実践しながら企画して提唱できるようになってもらいたいし、その結果、社会を変えていけるような人になってほしいと思います。
ソーシャルイノベーションデザイナーの資格を認証されるのは、一般財団法人地域公共人材開発機構(COLPU)と伺っていますが、COLPUはどのような組織ですか。
青山:「地域公共人材」を育成する仕組みを創造し、産官学民と協働しながら、社会全体の改革を目指して活動している団体です。京都地域の大学でアライアンスを作るにあたって地域のポリシーメイキングに携わる人たちのために「地域公共政策士」という新たな資格も作ろうと言う話になり、それを発行する第三者機関として2009年に設立しました。地域公共政策士の資格の元になったのはEQF(ヨーロピアンクォリフィケーションフレームワーク)です。EUの中にはいろんな国があり、それぞれに大学、専門学校、高校がありますが、同じ専門学校でもフランスとドイツが同じレベルかどうかはなかなかわかりにくいです。そこですべてをレベル化するフレームワークを作ったわけです。これによって違う国に行っても、その人のレベルがわかり、雇用を流動化できるようになりました。地域公共政策士もそれぞれの大学が用意したそれぞれのプログラムで学ぶので、レベルの差が生じやすいのですが、修了者に対し、COLPUが特別講義をして理解度を測り、最後にスクーリングを行い、本当にその能力を備えていると判断したうえで資格を発行しています。

宮本:各大学のそれぞれのプログラムで学ぶ地域公共政策士とは違い、今回のソーシャルイノベーションデザイナーは3大学が完全に連携していますので、龍谷大学、京都文教大学、琉球大学どこで学んでも同じプログラムとして審査します。
ソーシャルイノベーションデザイナーの資格があると、どのような場で活躍できますか。またどのような場で活躍してほしいですか。
的場:イノベーションはどこにでも必要なはずなので、可能性はいろいろとあります。現在の所属先から離れて新しい自分の事業をおこしていくこともできますし、今いる企業の中で、何かヒントを得てイノベーションを起こすこともできます。先ほども申しましたが、公務員の人たちもイノベーティブな発想で、政策や仕事の仕方を変えていくことができます。しかも今回のソーシャルイノベーションデザイナーのプログラムは、アート的な視点や臨床心理学の学びも取り入れており、イノベーションの捉え方次第でさまざまなところに活用できる資格です。講義も個人の興味や関心、自分が置かれている状況に合わせて取ることができます。
青山:さまざまな事例を知ることができるのも大きいですね。事例を知っていると発想が広がります。例えば長野県塩尻市では役所の職員が商店街の空き店舗でいろんなイベントをやり始め、商店街に賑わいが戻ってきたということがありました。地域の課題解決のために始めたことが地域の経済のためにもなったし、雇用を増やすことにもつながったのです。こういう事例を知っていると今すぐに実行できなくてもいつか役に立つことがある。宮本はこの前沖縄に行って、石垣島で実践してらっしゃる方の活動を視察してきたんですよね。
宮本:石垣の活性化プロジェクトです。石垣島の歴史などを掘り起して活動をされている方や地域の活動を取り上げている出版社や、ソーシャルビジネス的な発想で、自然環境の保護と地域経済の循環との両立を目指した活動をされている方など、自分たちで活動を興しておられる方のお話を聞かせていただきました。皆さん地域の特徴を生かし、地元にいかに還元するかを考えて活動されていらっしゃることが印象的でした。
的場:イノベーションには唯一の答えなどないですからね。その場、その場で違う。 たまたまここにはこういう人がいたとか、こういう関係性があったとか、そういうことも重要なので、我々からどこにでも通用する答えなんて提供できないわけですよ。 ただ青山先生おっしゃったみたいに事例をいっぱい知っていると、その中からいろんなヒントを得るチャンスが出てきます。このケースは使えるなとか、これとこのケースを併せれば、何か新しいことができるだろうなとか。そういったものをどんどんインプットすることによって、これまでにないイノベーティブな視点や論理的に考える力が養われます。あとうちの研究科の特徴ですが、いろいろな立場の人がいるので、大学院時代のネットワークが後になって役に立つことがあるんです。公務員の院生と企業の院生の間で、一緒に新たな事業を企画してみようといった議論に発展することはしばしばあります。そういうネットワークの力を生かせるのも大きいです。

青山:そのうえいろんな先生からの話も聞けるし、先生自身のネットワークもあるし、だからいろんなことが起こせるんですよね。的場先生がおっしゃるように龍谷大学は社会人院生たちがすごく多いから面白い。 私が研究科に在籍していたとき、学部から上がってきた院生たちが普段は絶対に巡り会えない人たちと巡り合って同じところで学び、ものすごく刺激になったと言っていました。 しかも今回のプログラムは、京都文教大学でメンタルヘルスを学んでいる人たちと、話し合える機会が持てるのもすごくいいと思います。去年イタリア・トリノに視察に行ったのですが、ソーシャルビジネスの団体がメンタルヘルス事業をやっている団体を支援していました。これからの企業は、やっぱりメンタルヘルスのことをもっともっと考えなきゃいけない、しかもそれがちゃんとビジネスになっているということがわかりました。
中森:みなさんがおっしゃるように、活躍できる場は本当に広いと思います。将来的には企業にソーシャル・イノベーションの専門部署みたいのができる。しかも そこにいる人たちのほとんどがソーシャルイノベーションデザイナーの資格を持っている、というような動きになってきたらいいですね。
青山:企業がソーシャルイノベーションデザイナーの資格を持った人を面接したことをきっかけに、「こういう人に入社してもらって、これから社会課題解決につながるような事業をやっていきたい」と思ってもらえるようなプラスになる資格として認知・定着していくことを期待しています。
育てる側、認める側がそれぞれ考える
ソーシャル・イノベーションを担う人材の証「ソーシャルイノベーションデザイナー」とは【前編】
[ 2025.3.24 更新 ]
ソーシャルイノベーションデザイナーという資格名に込められた思いや地域公共政策士との違いを具体的に教えてください。
青山:最近、様々な分野でプランニングをする人たちのことをデザイナーと呼ぶことが多くなってきたことを受け、ソーシャルイノベーションデザイナーと名付けました。
的場:自分自身が事業をデザインするだけではなく、ソーシャル・イノベーションの考え方を理解した上で今いる環境で新たなしくみをデザインする、といった能力も視野に入れています。
中森:ソーシャルイノベーションデザイナーと地域公共政策士は似ているといえば似ていますが、違う側面から見たら全く違うんですよね。地域公共政策士は公共政策をプランニングする人たちですが、近年、社会の課題が複雑化したことによって、条例を作る、補助金を出すといったこれまでの公共政策では解決できなくなってきた。その一方で民間企業は企業の社会的責任が意識されてきて社会に対して貢献しようという意欲が高まってきている。その社会課題解決に対する動きを事業として展開することで、持続的に続いていくものとなると考えています。
青山:少し前になりますが、イギリスでソーシャルビジネスという言葉が生まれましたよね。困っている人たちを支援する仕事を、公務員をしていた人が外に出てビジネスとしてやりはじめ、そして行政も社会課題の解決をビジネスとして成り立たせているところを支援するようになった。これがアメリカにも広がり、今ではたくさんのノンプロフィットの組織が社会的な事業をやっています。
私としては、企業だけでなくまだボランティア的なイメージが強い日本のNPOも、ビジネス的な視点を入れていけるといいのではないかなと思っています。このプログラムの授業で学んでいただいたことを、ビジネスにしていきましょうよ、ということですね。例えば今、国が推進している農福連携もビジネスとしてやっていくことが重要だと思います。
的場:その通りです。私としては公共事業や政策づくりに関わっている公務員の方にも、取得してほしいと思っています。青山先生がおっしゃったイギリスの公務員のように外に出ていってビジネスをしなくても、ソーシャル・イノベーション的なマインドを持つ事業を理解してそれをサポートするような政策を打つとか、公務員だからこそ可能なソーシャル・イノベーションの取り組みも色々とあると思います。
中森:地域公共政策士は行政や政治家、NPOの人たちが対象、ソーシャルイノベーションデザイナーは民間企業の人たちが対象と言ったら、きっとわかりやすいと思います。しかし、的場先生がおっしゃるように行政の人たちもこれからは事業マインドや事業スキルが必要ですし、民間企業は利己的で儲からないことには一切参加しないとなると、社会課題の解決というような長期的な目線での物事の判断ができなくなります。ですから地域公共政策士を民間企業の方々も取れる、公共の人たちがソーシャルイノベーションデザイナーも取れるようにしています。
的場:地域公共政策士と、より革新的なイメージがあるソーシャルイノベーションデザイナーの両方が取れることは研究科としても強みになりますし、学び手としても魅力的だと思います。ソーシャルイノベーションデザイナーの資格を目指す民間企業にお勤めの方には、NPOや公務員、議員など違うセクターの人たちと同じ教室で学んで、ソーシャル・イノベーションについて多様な視点から大いに議論していただきたいですね。
中森:それぞれの出口が違っても、地域の社会課題の解決に向けて、どうやったら解決できるのだろうかということを実践しながら企画して提唱できるようになってもらいたいし、その結果、社会を変えていけるような人になってほしいと思います。
ソーシャルイノベーションデザイナーの資格を認証されるのは、一般財団法人地域公共人材開発機構(COLPU)と伺っていますが、COLPUはどのような組織ですか。
青山:「地域公共人材」を育成する仕組みを創造し、産官学民と協働しながら、社会全体の改革を目指して活動している団体です。京都地域の大学でアライアンスを作るにあたって地域のポリシーメイキングに携わる人たちのために「地域公共政策士」という新たな資格も作ろうと言う話になり、それを発行する第三者機関として2009年に設立しました。地域公共政策士の資格の元になったのはEQF(ヨーロピアンクォリフィケーションフレームワーク)です。EUの中にはいろんな国があり、それぞれに大学、専門学校、高校がありますが、同じ専門学校でもフランスとドイツが同じレベルかどうかはなかなかわかりにくいです。そこですべてをレベル化するフレームワークを作ったわけです。これによって違う国に行っても、その人のレベルがわかり、雇用を流動化できるようになりました。地域公共政策士もそれぞれの大学が用意したそれぞれのプログラムで学ぶので、レベルの差が生じやすいのですが、修了者に対し、COLPUが特別講義をして理解度を測り、最後にスクーリングを行い、本当にその能力を備えていると判断したうえで資格を発行しています。
宮本:各大学のそれぞれのプログラムで学ぶ地域公共政策士とは違い、今回のソーシャルイノベーションデザイナーは3大学が完全に連携していますので、龍谷大学、京都文教大学、琉球大学どこで学んでも同じプログラムとして審査します。
ソーシャルイノベーションデザイナーの資格があると、どのような場で活躍できますか。またどのような場で活躍してほしいですか。
的場:イノベーションはどこにでも必要なはずなので、可能性はいろいろとあります。現在の所属先から離れて新しい自分の事業をおこしていくこともできますし、今いる企業の中で、何かヒントを得てイノベーションを起こすこともできます。先ほども申しましたが、公務員の人たちもイノベーティブな発想で、政策や仕事の仕方を変えていくことができます。しかも今回のソーシャルイノベーションデザイナーのプログラムは、アート的な視点や臨床心理学の学びも取り入れており、イノベーションの捉え方次第でさまざまなところに活用できる資格です。講義も個人の興味や関心、自分が置かれている状況に合わせて取ることができます。
青山:さまざまな事例を知ることができるのも大きいですね。事例を知っていると発想が広がります。例えば長野県塩尻市では役所の職員が商店街の空き店舗でいろんなイベントをやり始め、商店街に賑わいが戻ってきたということがありました。地域の課題解決のために始めたことが地域の経済のためにもなったし、雇用を増やすことにもつながったのです。こういう事例を知っていると今すぐに実行できなくてもいつか役に立つことがある。宮本はこの前沖縄に行って、石垣島で実践してらっしゃる方の活動を視察してきたんですよね。
宮本:石垣の活性化プロジェクトです。石垣島の歴史などを掘り起して活動をされている方や地域の活動を取り上げている出版社や、ソーシャルビジネス的な発想で、自然環境の保護と地域経済の循環との両立を目指した活動をされている方など、自分たちで活動を興しておられる方のお話を聞かせていただきました。皆さん地域の特徴を生かし、地元にいかに還元するかを考えて活動されていらっしゃることが印象的でした。
的場:イノベーションには唯一の答えなどないですからね。その場、その場で違う。 たまたまここにはこういう人がいたとか、こういう関係性があったとか、そういうことも重要なので、我々からどこにでも通用する答えなんて提供できないわけですよ。 ただ青山先生おっしゃったみたいに事例をいっぱい知っていると、その中からいろんなヒントを得るチャンスが出てきます。このケースは使えるなとか、これとこのケースを併せれば、何か新しいことができるだろうなとか。そういったものをどんどんインプットすることによって、これまでにないイノベーティブな視点や論理的に考える力が養われます。あとうちの研究科の特徴ですが、いろいろな立場の人がいるので、大学院時代のネットワークが後になって役に立つことがあるんです。公務員の院生と企業の院生の間で、一緒に新たな事業を企画してみようといった議論に発展することはしばしばあります。そういうネットワークの力を生かせるのも大きいです。
青山:そのうえいろんな先生からの話も聞けるし、先生自身のネットワークもあるし、だからいろんなことが起こせるんですよね。的場先生がおっしゃるように龍谷大学は社会人院生たちがすごく多いから面白い。 私が研究科に在籍していたとき、学部から上がってきた院生たちが普段は絶対に巡り会えない人たちと巡り合って同じところで学び、ものすごく刺激になったと言っていました。 しかも今回のプログラムは、京都文教大学でメンタルヘルスを学んでいる人たちと、話し合える機会が持てるのもすごくいいと思います。去年イタリア・トリノに視察に行ったのですが、ソーシャルビジネスの団体がメンタルヘルス事業をやっている団体を支援していました。これからの企業は、やっぱりメンタルヘルスのことをもっともっと考えなきゃいけない、しかもそれがちゃんとビジネスになっているということがわかりました。
中森:みなさんがおっしゃるように、活躍できる場は本当に広いと思います。将来的には企業にソーシャル・イノベーションの専門部署みたいのができる。しかも そこにいる人たちのほとんどがソーシャルイノベーションデザイナーの資格を持っている、というような動きになってきたらいいですね。
青山:企業がソーシャルイノベーションデザイナーの資格を持った人を面接したことをきっかけに、「こういう人に入社してもらって、これから社会課題解決につながるような事業をやっていきたい」と思ってもらえるようなプラスになる資格として認知・定着していくことを期待しています。