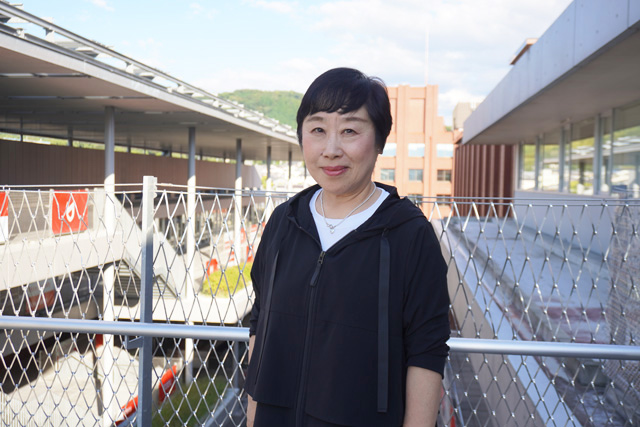
ソーシャル・イノベーション人材養成プログラムではどのような科目が学べますか?
心理学の大学院を卒業して、働く人のメンタルヘルスを支援するための仕事をしている、あるいは、臨床心理士や公認心理師の資格があり将来産業領域で仕事したいと思っている人たちが受講する研究所の講座をベースに科目を組みました。産業領域は、はたらく人のメンタルヘルスが対象となるため、鬱や適応障害だけでなく、発達の問題、家族の問題、職場の人間関係、キャリア、子育てや介護との両立、ハラスメント、などメンタル不調の背景の因子が複雑になってきているので、講師はさまざまな専門家が揃っています。例えば、組織心理コンサルテーション、コーチング論、裁判事例にみるメンタルヘルスの法律問題、産業心身医学、キャリアデザイン論、エグゼクティブカウンセリングなどがあります。
面白そうですね。先生のご専門はなんですか?
私の専門は臨床神経心理学、高次脳機能障害学です。突然の事故や病気などによる脳の損傷によって高次脳機能障害となった方の心理面、認知面の回復をめざす神経心理学的リハビリテーションを担当しています。プログラムでは「産業領域における高次脳機能障害学」では、高次脳機能障害の方の職場復帰支援を通して、キャリア支援について検討していきます。
産業精神保健分野における心理学から深層心理学まで幅広い心理学の領域が学べると言うことですね。今回ソーシャルイノベーション人材養成プログラムを学ぶ人にとって、どういうメリットがあるとお考えですか?
ソーシャル・イノベーションというと、オーバーツーリズムなどの社会課題が注目されますが、組織の中にも課題があります。社員のメンタルヘルスのためには、組織的の中にある小さなところに目を向けて、みんなの働きやすさを追求していくことも大事です。居心地が良かったり、発言しやすかったりする職場は、アイデアもどんどん出てくると思います。仕事でミスした時に、相談できる人がいると心理的安全性が保たれる職場になりますね。人間関係の希薄化を予防するための対話型組織開発のメンタルヘルスでは、「こういう職場だったらいいよね」と、みんなで理想の状態を放談する(言いっぱなし)。評価しない。誰でもできる。オフィスにコーヒーが飲める場所があったらコーヒーを飲みながら放談する。知らない部署の人ともおしゃべりする。会議のように議題を話し合うのではなく、おしゃべりの中にヒントを見つける。そうするうちに関係も良くなってくる。

話をするだけで変わるんですか?
実際に学会で報告があった事例なんですが、ある会社がストレスチェックを行ってみたところ、高ストレス者が多い部署があった。そこで、あれがあったらいいよねとか、時間に余裕があったらいいよね、フレックスみたいに早く帰れたらいいよね、というような願望をただただ言い合う時間を週に1回、30分だけ設けてみたら、2年後のその部署のストレス数値が良くなったんです。1980年代にアメリカで生まれた対話型組織開発のメンタルヘルスは現在、日本の企業でも取り入れているところが増えてきています。
仕事から離れた大きな取り組みをしなくても、課題解決のためのアイデアを提案できる例です。お金をかけることなく、ただ願望を言い合う時間を作るという仕事場の中でやれることで社員のストレスを軽減するのも社内イノベーションかもしれません。
心理学の奥深さの一端を垣間見た気がします
心理学は、自分の目が内に向かうことを支援することで、自分の気持ち、自分の足元、自分の周りなどを見つめ直し、自分の組織など、身近なところを見る視点が変わることもあります。これまで気づかなかったところへの気づきにつながったりします。
見つめ直すとはどういうことですか?
例えで言うと、人はストライクゾーンばかりを見がちですが、ストライクゾーンの外に何かヒントがあるかもしれませんのでストライクゾーンの外に見るようにしています。
例えば、若い社員とのコミュニケーションはこうすればいい、仕事がうまくいかない社員にはこう伝えたらいい、というハウツー的なものがストライクゾーンだとします。それを相手は何を考えているのか、失敗したことをどう捉えているか、など相手に聞いてみることが大事と捉えると、相手の話を聞くことで、こんな伝え方を求めているのだとわかることがあります。
先ほど言っておられたオーバーツーリズムみたいな社会課題の中にもストライクゾーンではない見方ができると?
文化や生活の仕様が違うさまざまな国籍の人に対応するホテルの人のストレス度ってどうなんだろうかということに目を向けてみる。トラブルがあって注意しなければいけないけれど、注意の仕方によっては逆に何かクレームを言われたりすることもあるだろうし、悪い評判はすぐにSNSで広まってしまうから気が抜けない。これは交通渋滞をどうするか、ゴミや環境破壊などのトラブルをどうするかといった課題とは異なり、ストライクゾーンの外にある問題と捉えることもできます。
ある事件に遭遇した被害者や家族のことを考えるのがストライクゾーンだとしたら、傷ついた方々に接する仕事に就いた医師や歯科医、作業に携わった人たちの心のケアは誰がしているのかなと考えることもあります。仕事ではあっても、事件後の心のケアが必要になってくると思います。支援者も元の仕事場に戻っていけるようにしてあげるというのも大事な支援だと思います。
以前、京都文教大学、龍谷大学、琉球大学の3大学の先生たちの座談会で、将来的にチームで何かを動かすということになったとき、ビジネスを考える人たちの中に心理的な要素からアプローチできる人がいることによって、本当のイノベーションを起こせるのではないかっていう話をされてらっしゃいました。
心理学、経営学、環境学の一つの学問だけでなく、いろいろな科目を受講することで受ける刺激によるシナジー効果が起こると考えています。
そして、何か新しいことをしようと思ったときに、京都の強みがあると思います。新しいことを取り入れながら伝統を守っていくための努力など、経営者の方とお話すると教えて頂くことが多いです。
3大学が連携する「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」は広く門戸が開かれたプログラムです。そしてさまざまな課題の中で、新しい何かに取り組み続ける京都という地で学べます。ソーシャル・イノベーションに少しでも興味があるなら、ぜひ履修してみてください。
ありがとうございました。
ソーシャル・イノベーションにおける
心理学の役割と意義について京都文教大学 産業メンタルヘルス研究所
中島恵子所長にインタビュー【後編】
[ 2025.1.8 更新 ]
ソーシャル・イノベーション人材養成プログラムではどのような科目が学べますか?
心理学の大学院を卒業して、働く人のメンタルヘルスを支援するための仕事をしている、あるいは、臨床心理士や公認心理師の資格があり将来産業領域で仕事したいと思っている人たちが受講する研究所の講座をベースに科目を組みました。産業領域は、はたらく人のメンタルヘルスが対象となるため、鬱や適応障害だけでなく、発達の問題、家族の問題、職場の人間関係、キャリア、子育てや介護との両立、ハラスメント、などメンタル不調の背景の因子が複雑になってきているので、講師はさまざまな専門家が揃っています。例えば、組織心理コンサルテーション、コーチング論、裁判事例にみるメンタルヘルスの法律問題、産業心身医学、キャリアデザイン論、エグゼクティブカウンセリングなどがあります。
面白そうですね。先生のご専門はなんですか?
私の専門は臨床神経心理学、高次脳機能障害学です。突然の事故や病気などによる脳の損傷によって高次脳機能障害となった方の心理面、認知面の回復をめざす神経心理学的リハビリテーションを担当しています。プログラムでは「産業領域における高次脳機能障害学」では、高次脳機能障害の方の職場復帰支援を通して、キャリア支援について検討していきます。
産業精神保健分野における心理学から深層心理学まで幅広い心理学の領域が学べると言うことですね。今回ソーシャルイノベーション人材養成プログラムを学ぶ人にとって、どういうメリットがあるとお考えですか?
ソーシャル・イノベーションというと、オーバーツーリズムなどの社会課題が注目されますが、組織の中にも課題があります。社員のメンタルヘルスのためには、組織的の中にある小さなところに目を向けて、みんなの働きやすさを追求していくことも大事です。居心地が良かったり、発言しやすかったりする職場は、アイデアもどんどん出てくると思います。仕事でミスした時に、相談できる人がいると心理的安全性が保たれる職場になりますね。人間関係の希薄化を予防するための対話型組織開発のメンタルヘルスでは、「こういう職場だったらいいよね」と、みんなで理想の状態を放談する(言いっぱなし)。評価しない。誰でもできる。オフィスにコーヒーが飲める場所があったらコーヒーを飲みながら放談する。知らない部署の人ともおしゃべりする。会議のように議題を話し合うのではなく、おしゃべりの中にヒントを見つける。そうするうちに関係も良くなってくる。
話をするだけで変わるんですか?
実際に学会で報告があった事例なんですが、ある会社がストレスチェックを行ってみたところ、高ストレス者が多い部署があった。そこで、あれがあったらいいよねとか、時間に余裕があったらいいよね、フレックスみたいに早く帰れたらいいよね、というような願望をただただ言い合う時間を週に1回、30分だけ設けてみたら、2年後のその部署のストレス数値が良くなったんです。1980年代にアメリカで生まれた対話型組織開発のメンタルヘルスは現在、日本の企業でも取り入れているところが増えてきています。
仕事から離れた大きな取り組みをしなくても、課題解決のためのアイデアを提案できる例です。お金をかけることなく、ただ願望を言い合う時間を作るという仕事場の中でやれることで社員のストレスを軽減するのも社内イノベーションかもしれません。
心理学の奥深さの一端を垣間見た気がします
心理学は、自分の目が内に向かうことを支援することで、自分の気持ち、自分の足元、自分の周りなどを見つめ直し、自分の組織など、身近なところを見る視点が変わることもあります。これまで気づかなかったところへの気づきにつながったりします。
見つめ直すとはどういうことですか?
例えで言うと、人はストライクゾーンばかりを見がちですが、ストライクゾーンの外に何かヒントがあるかもしれませんのでストライクゾーンの外に見るようにしています。
例えば、若い社員とのコミュニケーションはこうすればいい、仕事がうまくいかない社員にはこう伝えたらいい、というハウツー的なものがストライクゾーンだとします。それを相手は何を考えているのか、失敗したことをどう捉えているか、など相手に聞いてみることが大事と捉えると、相手の話を聞くことで、こんな伝え方を求めているのだとわかることがあります。
先ほど言っておられたオーバーツーリズムみたいな社会課題の中にもストライクゾーンではない見方ができると?
文化や生活の仕様が違うさまざまな国籍の人に対応するホテルの人のストレス度ってどうなんだろうかということに目を向けてみる。トラブルがあって注意しなければいけないけれど、注意の仕方によっては逆に何かクレームを言われたりすることもあるだろうし、悪い評判はすぐにSNSで広まってしまうから気が抜けない。これは交通渋滞をどうするか、ゴミや環境破壊などのトラブルをどうするかといった課題とは異なり、ストライクゾーンの外にある問題と捉えることもできます。
ある事件に遭遇した被害者や家族のことを考えるのがストライクゾーンだとしたら、傷ついた方々に接する仕事に就いた医師や歯科医、作業に携わった人たちの心のケアは誰がしているのかなと考えることもあります。仕事ではあっても、事件後の心のケアが必要になってくると思います。支援者も元の仕事場に戻っていけるようにしてあげるというのも大事な支援だと思います。
以前、京都文教大学、龍谷大学、琉球大学の3大学の先生たちの座談会で、将来的にチームで何かを動かすということになったとき、ビジネスを考える人たちの中に心理的な要素からアプローチできる人がいることによって、本当のイノベーションを起こせるのではないかっていう話をされてらっしゃいました。
心理学、経営学、環境学の一つの学問だけでなく、いろいろな科目を受講することで受ける刺激によるシナジー効果が起こると考えています。
そして、何か新しいことをしようと思ったときに、京都の強みがあると思います。新しいことを取り入れながら伝統を守っていくための努力など、経営者の方とお話すると教えて頂くことが多いです。
3大学が連携する「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」は広く門戸が開かれたプログラムです。そしてさまざまな課題の中で、新しい何かに取り組み続ける京都という地で学べます。ソーシャル・イノベーションに少しでも興味があるなら、ぜひ履修してみてください。
ありがとうございました。