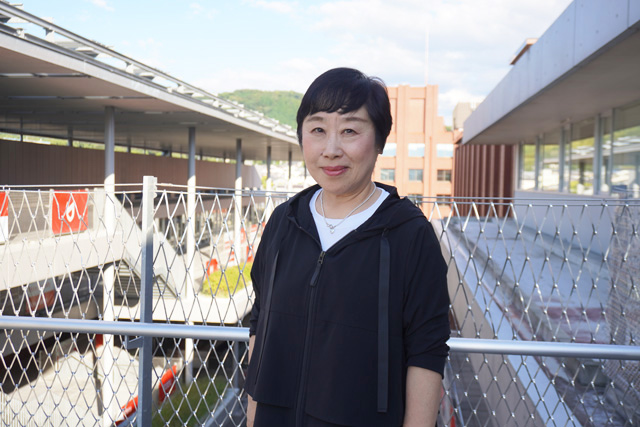
京都文教大学大学院臨床心理学研究科の特徴を教えてください。
臨床心理職の専門家である臨床心理士養成する大学院として、2000年の設立以来600人以上の専門家を輩出しています。
学びの特徴は、深層心理学、力動的心理療法をベースとした心理療法、とりわけユング心理学が得意とする非言語的方法、箱庭療法をはじめとする芸術療法などを体験的に学べることです。
私が所長を務めている「産業メンタルヘルス研究所」は大学付設機関で、産業領域の心理職対象の養成講座、人事・総務・経営者層対象のラインケア研修、企業訪問、企業懇談会、大学院生の産業臨床活動、学内ワークショップなどの活動をしております。
京都文教大学が提携する「ともいきパートナーズ」で行った25社へのアンケート調査で面白い結果が出たと伺いました。
「京都文教ともいきパートナーズ」は地元企業、経済団体、行政との連携を図る京都文教大学独自の地域ネットワークなのですが、これに参加していただいている企業を対象に、「中小企業が求めるソーシャル・イノベーション人材」とは、というアンケート調査を行いました。その結果、一番になったのが人間性、2番目が協調性、3番目がリーダーシップ、4つ目が問題を解決する力でした。ツールやスキルなど、技術力や専門性の高さなどではなく人間性。私は心理学が専門なので「まずは人間性」と考えているのですが、経営者も同じように人間性を望んでいることがわかり、安心しました。
働く中で、これがわかる、これを知っている、これができる、というのも大事なのですが、その背景には必ず人と人との関係がある。経営者はそれをわかっているからこそ、人柄や協力してやっていこうとする協調性を望んでいるんですね。
もちろんビジネスとして収益や利益を上げなくてはならないですから、世の中のニーズをキャッチアップできる能力も大切です。しかし、コロナ禍のように思いがけないことが起こり、今までのような活動ができなくなってきたときに,企業を支えるものは何かというと、危機を乗り越えていこうと協力する力や何とか会社をやっていこうとする想いみたいなものだと思います。
人間性と協調性があるのは、企業の底力として非常に強いということですか?
そうですね。景気が良いときは、新しいものをどんどん生み出したりして収益に結びついていくけれど、不測の事態って起こるわけじゃないですか。そのときに、普段は発言もしなかったような人がこんなことしたらどうかとか言ってみたり、みんなでいろんな知恵を出し合ったり、一緒に働く人たちが力を合わせることで、苦難を乗り切る大きな力になるかもしれません。機器が新しくなって便利になるとか、AIがより進化して社会が変わるということだけがイノベーションじゃなくて、人間の関係性によってもイノベーションは起こると考えています。
人間性や協調性が大切だと昔から言われていますけど、現在の社会においても不変なのですね。3番目に必要とされたリーダーシップもまた、昔から大切な要素として挙げられていますが。
リーダーシップというと困難に陥った時に強い力でみんなを引っ張っていくというのが、一般的なイメージでしょう。スタンフォード大学の名誉教授ヤーロムは、リーダーシップを4つの心理機能で説明しています。その中で、「意味づけ」と「配慮」が大切だと述べています。「実行力」やみんなの気持ちを鼓舞するような「情緒的な刺激」も必要です。しかし、みんなが自発的に動く組織になるためには、「意味づけ」と[配慮]が欠かせないと述べています。
リーダーシップというと、「自分の背中を見て、ついてこい」というイメージを持っていました。具体的に意味づけとはどういうことなんでしょう。
先日、私が教えている学生が、推し活のために3日連続で神戸に行ってきたと話してくれました。「夜遅くなったせいで授業中ちょっと寝ちゃいました」なんて言いながら、3日間の出来事をものすごくいきいきと話すのです。いきいきと話すということは、推し活がその学生さんにとってエネルギーになっているわけですね。そこで「推し活は、あなたのエネルギー源になって、勉学の力にもなるね」と言いました。これが意味づけです。「試験があるのに夜遅く、神戸まで行ったの?」「授業はちゃんと出られたの?」と返してしまうと推し活が良くないものになってしまう。でもいきいきと話すような体験をした学生に、エネルギー源になっているねって伝えると、推し活は私のエネルギーになっている、それが勉強のエネルギーにもなるって思える。
意味づけをしてくれると、自分がやっていることを肯定的な意味で捉えることができる。社員が行き詰まっている時も、それはこういう意味でとらえられるのではないか、こんなふうに考えられるのではないか、と意味づければ別の見方をするための経験と捉えてもらえます。意味づけはコーチングに近いのかもしれません。自分の考えで自分の息を詰めてしまっていると捉えると、社員の方が主体的に動いていくのを助けることにつながるのかもしれません。

意味づけをするには、まずコミュニケーションが大切ですね。
管理職研修でもどう話しかけたらいいんですか、どう聞き出せばいいんですか、とよく質問されます。コミュニケーションって、話しかける、聞き出すことではなく、相手が話したいことをまずは受け止めて聞くことから始まります。管理職ばかり話している場面を見て頂き、どんな感じを持ったかを話してもらうといいですね。まずは、話す割合が、社員が7割、管理職は3割だと、社員の方は管理職と話したと実感するでしょう。
一方的に話しかけるのは違うということですね。
中小企業の経営者の中には、社員とはよくコミュニケーションは取れています。朝はおはようと挨拶しています、みんなと話をしています、と言われるのですが、案外、一方的であったりもします。それぞれの社員の方がどう思っているか、どう考えているか、10人いたら10人の社員の違いみたいなものを把握しながらお話していますかと聞いてみるようにしています。相手がどう思っているのか、どんな気持ちで働いているのか、配慮と意味づけを意識して対応すると、関係性はぐんと良くなります。
自分の経験談を話す時も、まずは相手の話を聞いて、自分の経験が役に立ちそうだと思った時に伝えるといいですね。求めているものを話してもらうと、元気になり、主体的に動こうとすると思います。
それは配慮のひとつでもありますよね。配慮と意味づけは、思いやりと言いますか、相手に尊重することに近いですね。
「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」は、龍谷大学からお誘い頂き連携が始まりました。政策学研究科の中森研究科長とは「やましろオンリーワン倶楽部」で出会い、中森先生の経営学の講義を拝聴しました。「経営で一番気になるのは利益を上げることでしょうけれど、それは社員同士の思いやりとか優しさとか、そういうものが基盤にないと仕事って積み上げていけないものなんだ」と言われました。優しさとか思いやりって、配慮と意味づけが必要ですね。。経営学の先生のお話を聞くのは初めてだったので、経営学と心理学の共通点が見つかり嬉しかったです。しかも「目に見える合理的なものではなく、思いやりと優しさ、つまり目に見えないものを“非合理のすすめ”ということで僕は推奨しているんです。事業がずっと持続していくためには、この土台がないとうまくいかないんです」と言われました。経営学の話なのに、心理学の話をされてると感銘を受け、お話がはずみました。それが今回の事業につながりました。
経営学と心理学は密接につながっているものなのですね。今回、ソーシャル・イノベーション人材養成プログラムに心理学で有数の大学である京都文教大学と連携した理由がわかりました。
引き続き、ソーシャルイノベーション人材養成プログラムについて伺いたいと思います。
ソーシャル・イノベーションにおける
心理学の役割と意義について京都文教大学 産業メンタルヘルス研究所
中島恵子所長にインタビュー【前編】
[ 2025.1.7 更新 ]
京都文教大学大学院臨床心理学研究科の特徴を教えてください。
臨床心理職の専門家である臨床心理士養成する大学院として、2000年の設立以来600人以上の専門家を輩出しています。
学びの特徴は、深層心理学、力動的心理療法をベースとした心理療法、とりわけユング心理学が得意とする非言語的方法、箱庭療法をはじめとする芸術療法などを体験的に学べることです。
私が所長を務めている「産業メンタルヘルス研究所」は大学付設機関で、産業領域の心理職対象の養成講座、人事・総務・経営者層対象のラインケア研修、企業訪問、企業懇談会、大学院生の産業臨床活動、学内ワークショップなどの活動をしております。
京都文教大学が提携する「ともいきパートナーズ」で行った25社へのアンケート調査で面白い結果が出たと伺いました。
「京都文教ともいきパートナーズ」は地元企業、経済団体、行政との連携を図る京都文教大学独自の地域ネットワークなのですが、これに参加していただいている企業を対象に、「中小企業が求めるソーシャル・イノベーション人材」とは、というアンケート調査を行いました。その結果、一番になったのが人間性、2番目が協調性、3番目がリーダーシップ、4つ目が問題を解決する力でした。ツールやスキルなど、技術力や専門性の高さなどではなく人間性。私は心理学が専門なので「まずは人間性」と考えているのですが、経営者も同じように人間性を望んでいることがわかり、安心しました。
働く中で、これがわかる、これを知っている、これができる、というのも大事なのですが、その背景には必ず人と人との関係がある。経営者はそれをわかっているからこそ、人柄や協力してやっていこうとする協調性を望んでいるんですね。
もちろんビジネスとして収益や利益を上げなくてはならないですから、世の中のニーズをキャッチアップできる能力も大切です。しかし、コロナ禍のように思いがけないことが起こり、今までのような活動ができなくなってきたときに,企業を支えるものは何かというと、危機を乗り越えていこうと協力する力や何とか会社をやっていこうとする想いみたいなものだと思います。
人間性と協調性があるのは、企業の底力として非常に強いということですか?
そうですね。景気が良いときは、新しいものをどんどん生み出したりして収益に結びついていくけれど、不測の事態って起こるわけじゃないですか。そのときに、普段は発言もしなかったような人がこんなことしたらどうかとか言ってみたり、みんなでいろんな知恵を出し合ったり、一緒に働く人たちが力を合わせることで、苦難を乗り切る大きな力になるかもしれません。機器が新しくなって便利になるとか、AIがより進化して社会が変わるということだけがイノベーションじゃなくて、人間の関係性によってもイノベーションは起こると考えています。
人間性や協調性が大切だと昔から言われていますけど、現在の社会においても不変なのですね。3番目に必要とされたリーダーシップもまた、昔から大切な要素として挙げられていますが。
リーダーシップというと困難に陥った時に強い力でみんなを引っ張っていくというのが、一般的なイメージでしょう。スタンフォード大学の名誉教授ヤーロムは、リーダーシップを4つの心理機能で説明しています。その中で、「意味づけ」と「配慮」が大切だと述べています。「実行力」やみんなの気持ちを鼓舞するような「情緒的な刺激」も必要です。しかし、みんなが自発的に動く組織になるためには、「意味づけ」と[配慮]が欠かせないと述べています。
リーダーシップというと、「自分の背中を見て、ついてこい」というイメージを持っていました。具体的に意味づけとはどういうことなんでしょう。
先日、私が教えている学生が、推し活のために3日連続で神戸に行ってきたと話してくれました。「夜遅くなったせいで授業中ちょっと寝ちゃいました」なんて言いながら、3日間の出来事をものすごくいきいきと話すのです。いきいきと話すということは、推し活がその学生さんにとってエネルギーになっているわけですね。そこで「推し活は、あなたのエネルギー源になって、勉学の力にもなるね」と言いました。これが意味づけです。「試験があるのに夜遅く、神戸まで行ったの?」「授業はちゃんと出られたの?」と返してしまうと推し活が良くないものになってしまう。でもいきいきと話すような体験をした学生に、エネルギー源になっているねって伝えると、推し活は私のエネルギーになっている、それが勉強のエネルギーにもなるって思える。
意味づけをしてくれると、自分がやっていることを肯定的な意味で捉えることができる。社員が行き詰まっている時も、それはこういう意味でとらえられるのではないか、こんなふうに考えられるのではないか、と意味づければ別の見方をするための経験と捉えてもらえます。意味づけはコーチングに近いのかもしれません。自分の考えで自分の息を詰めてしまっていると捉えると、社員の方が主体的に動いていくのを助けることにつながるのかもしれません。
意味づけをするには、まずコミュニケーションが大切ですね。
管理職研修でもどう話しかけたらいいんですか、どう聞き出せばいいんですか、とよく質問されます。コミュニケーションって、話しかける、聞き出すことではなく、相手が話したいことをまずは受け止めて聞くことから始まります。管理職ばかり話している場面を見て頂き、どんな感じを持ったかを話してもらうといいですね。まずは、話す割合が、社員が7割、管理職は3割だと、社員の方は管理職と話したと実感するでしょう。
一方的に話しかけるのは違うということですね。
中小企業の経営者の中には、社員とはよくコミュニケーションは取れています。朝はおはようと挨拶しています、みんなと話をしています、と言われるのですが、案外、一方的であったりもします。それぞれの社員の方がどう思っているか、どう考えているか、10人いたら10人の社員の違いみたいなものを把握しながらお話していますかと聞いてみるようにしています。相手がどう思っているのか、どんな気持ちで働いているのか、配慮と意味づけを意識して対応すると、関係性はぐんと良くなります。
自分の経験談を話す時も、まずは相手の話を聞いて、自分の経験が役に立ちそうだと思った時に伝えるといいですね。求めているものを話してもらうと、元気になり、主体的に動こうとすると思います。
それは配慮のひとつでもありますよね。配慮と意味づけは、思いやりと言いますか、相手に尊重することに近いですね。
「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」は、龍谷大学からお誘い頂き連携が始まりました。政策学研究科の中森研究科長とは「やましろオンリーワン倶楽部」で出会い、中森先生の経営学の講義を拝聴しました。「経営で一番気になるのは利益を上げることでしょうけれど、それは社員同士の思いやりとか優しさとか、そういうものが基盤にないと仕事って積み上げていけないものなんだ」と言われました。優しさとか思いやりって、配慮と意味づけが必要ですね。。経営学の先生のお話を聞くのは初めてだったので、経営学と心理学の共通点が見つかり嬉しかったです。しかも「目に見える合理的なものではなく、思いやりと優しさ、つまり目に見えないものを“非合理のすすめ”ということで僕は推奨しているんです。事業がずっと持続していくためには、この土台がないとうまくいかないんです」と言われました。経営学の話なのに、心理学の話をされてると感銘を受け、お話がはずみました。それが今回の事業につながりました。
経営学と心理学は密接につながっているものなのですね。今回、ソーシャル・イノベーション人材養成プログラムに心理学で有数の大学である京都文教大学と連携した理由がわかりました。
引き続き、ソーシャルイノベーション人材養成プログラムについて伺いたいと思います。