-2025年に開講する大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラムへの思いをお聞かせください。
深尾:龍谷大学は長期ビジョンの中で「社会変革の中核的担い手になる」と明言しています。つまり、社会変革のハブになる発想です。このような大学は日本中探しても類をみないと思います。自治体や企業なんかも巻き込んで展開する今回のプログラムは社会変革のハブになるために重要だと考えています。
丹波:龍谷大学大学院の政策学研究コースが、その役割を担っていたと思うんですけど、今回のプログラムによって政策学研究コースのウリが少なくなるのでは?と考えたりしています。

深尾:単体の大学院では教員の数も限られていますし、いろんな人たちと繋がらないとできないこともある。でも今回のプログラムのように、他の大学と連携するということでかなり広がっていくわけですよ。京都文教大学の心理学という強み、地域のいろんな矛盾の向き合い続ける琉球大学の強みを我々が共有することで、新たな何かを生み出し政策学研究科全体にフィードバックされていくと思います。ウリが少なくなるというより、今後自分たちがやりたい研究科の姿に歩みを進める上で非常に強い力になると思いますし、研究科自体の学びもバージョンアップするのではと期待しています。
木原:私は龍谷大学の大学院で学んだので、信頼度は高いのですが、ソーシャル・イノベーションを起こす力が、このプログラムで学ぶだけで本当に鍛えられるものなのか、これに関してはちょっと疑問を呈したいのですが、いかがでしょう。
深尾:プログラムの中で完成するというものでなくていいんですよ。現場や社会を知っている人が、何かヒントをもらう、教授陣をはじめいろんな知見がある中で自分のことを整理するきっかけになれば。このプログラムは単なる養成講座ではないと思うので、さまざまな人や課題に触れて、ものの見方や考え方に刺激を受けながら、一生をかけて思考していく人たちを増やしていきたいと思います。
木原:なるほど。私は大学時代、勉強そっちのけで小学校を回って温暖化の出前授業をやっていて、卒業後NPOの事務局長になったんですが、学ばないとまずいなと思って大学院に入ったんです。その中で社会に対して真剣に怒れる人や、海外で活動している人や、社会をなんとかするために人と組織を育てようと頑張っている人などいろんな人からいい刺激を受けました。
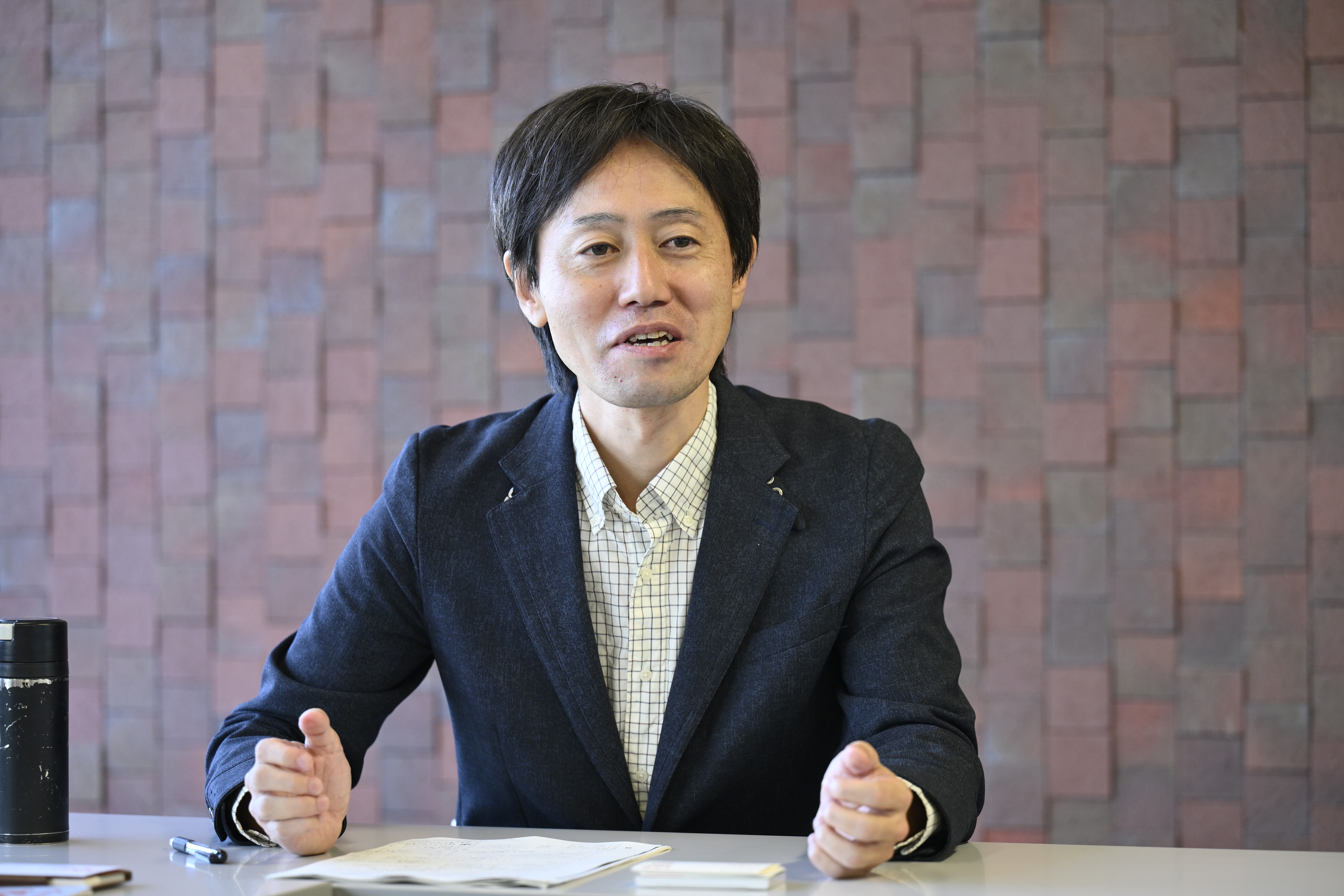
住友:現場を経験して学ぶのは全然違いますよ。それはすごくわかります。学生と違って、社会に出てから学ぶというのは本当に気持ちがあるんで、吸収力が違うでしょう。僕は23歳の時から雑誌づくりを始めましたけど、最初は全くの素人だった。だからあらゆる研修や勉強会に出ましたし、コンサルティングもお願いしました。決して安くはなかったですが、それをゼロにするか、ギャラを何倍にするかは自分次第なんですよ。それは大学も一緒ですね。お金を出して学んだことをどう使うかという。
玉城:僕は今、勉強したいなと思います。大学のときはほとんど勉強してなくて。社会人になって、こうやって通える場所があるのはうらやましい。ソーシャル・イノベーションのプログラムの中で実際にある社会課題についてみんなで一緒に考えていけけるのもいいと思います。いろんなものに触れる機会も多くなるでしょうし、自分が気づかなかったことにも気づくきっかけが学ぶことによって見つかるような気がします。自分から求めないと、というのはどこに行っても同じですが、そうさせてくれる環境があるというのはとてもいいと思います。
住友:こういうプログラムは教える側の立ち位置というか、基準がどこにあるかが大きく影響しますよね。
深尾:今までの大学教育の枠組みではできないという覚悟はあります。実は社会人も対象とした大学院をやっている時点で、多くの教員が感じていることなんですよ。実社会の中で課題や意識を持っている社会人に対して、浮世離れしたことだけ教えてもニーズに応えられず学生も来ません。だから既存の大学教員だけでは足りない部分は、自治体や企業とパートナーシップを組んでいきたいと思います。このプログラムはある意味、大学教員が問われる、刃が自分たちに向いてくる、むしろ向けながら取り組まなくてはいけないと一教員として考えています。
-ソーシャル・イノベーションを大学で教える、ソーシャルイノベーターを大学で育てるということは大変なことだということを理解しました。そのうえで龍谷大学としてどのようなことを学んでほしいと思いますか?
深尾:龍谷大学は市民社会と共に学んできた大学なんですね。仏教系の大学ということもあって、これまでも犯罪を犯した人たちの更生を一緒になって考えたり、市民運動やNPOの人たちに学びの機会を提供したりすることやってきました。今までの大学の役割とは違う、いろんな人たちが来てくれるこの環境は学部の教育や学生たちの教育に、ものすごく生きていると感じています。今回は大学院のプログラムなので、教えるのではなく一緒になって悩んだり、考えたりすることが求められる。我々が今、このプログラムで規定しているソーシャル・イノベーションが、いい意味でどんどん裏切られていってほしいですね。
住友:想定を超えてくるという期待ですね。ところで今の学生って議論します?
深尾:二極化していますね。受験戦争的な価値で入学した学生は議論が苦手ですが、実はそうじゃない学生が増えてきているんです。その背景にあるのは、高校までの学び方が変わってきたということ。これまで大学に来なかったような人たち、例えば不登校でフリースクールに通っていた子や通信制高校などのラインですね。そういう、今までと違う層の学生は、ものすごく感受性が豊かで、議論できる。そういう意味で非常に面白くなっています。僕は不登校をしている子は、ある意味イノベーターだと思っています。あの年で、身を挺して社会や学校に反抗しているわけですから。その反抗によって大人たちは初めて教育に問題があるのでは、と気づけるんですよね。彼らがレジスタンスとして戦った結果、学校にとらわれない学び方ができるようになった。これがソーシャル・イノベーションだとも思います。苦しんだ、いじめられた、ということを踏まえて、チャンスをもぎ取ってきた人を、すごいなって言ってあげられる社会や教育じゃないといけないなと思います。
住友:僕の知っているフリースクールの卒業生たちが現場で活躍し始めているんですけど、彼らは摩擦を嫌うんです。みんなケンカをしない、いい子なんです。僕がちょっときついこと言うと「昭和のじじいはきつすぎ」と思ってしまう。ちょっと壁に当たると絶対乗り越えられないって心配になるんですよね。だって世の中汚い輩がいっぱいいるじゃないですか。起業された方って必ずそういう人とぶち当たってきていると思うし、正面切ってケンカしないといけない。だから議論する経験を積むっていうことは大切だし、世の中にいるダークな連中に近づく必要はないけれども、そういう存在がいるということはやっぱり知るべきだと思います。それと、どんどん海外にも行ってほしいですね。
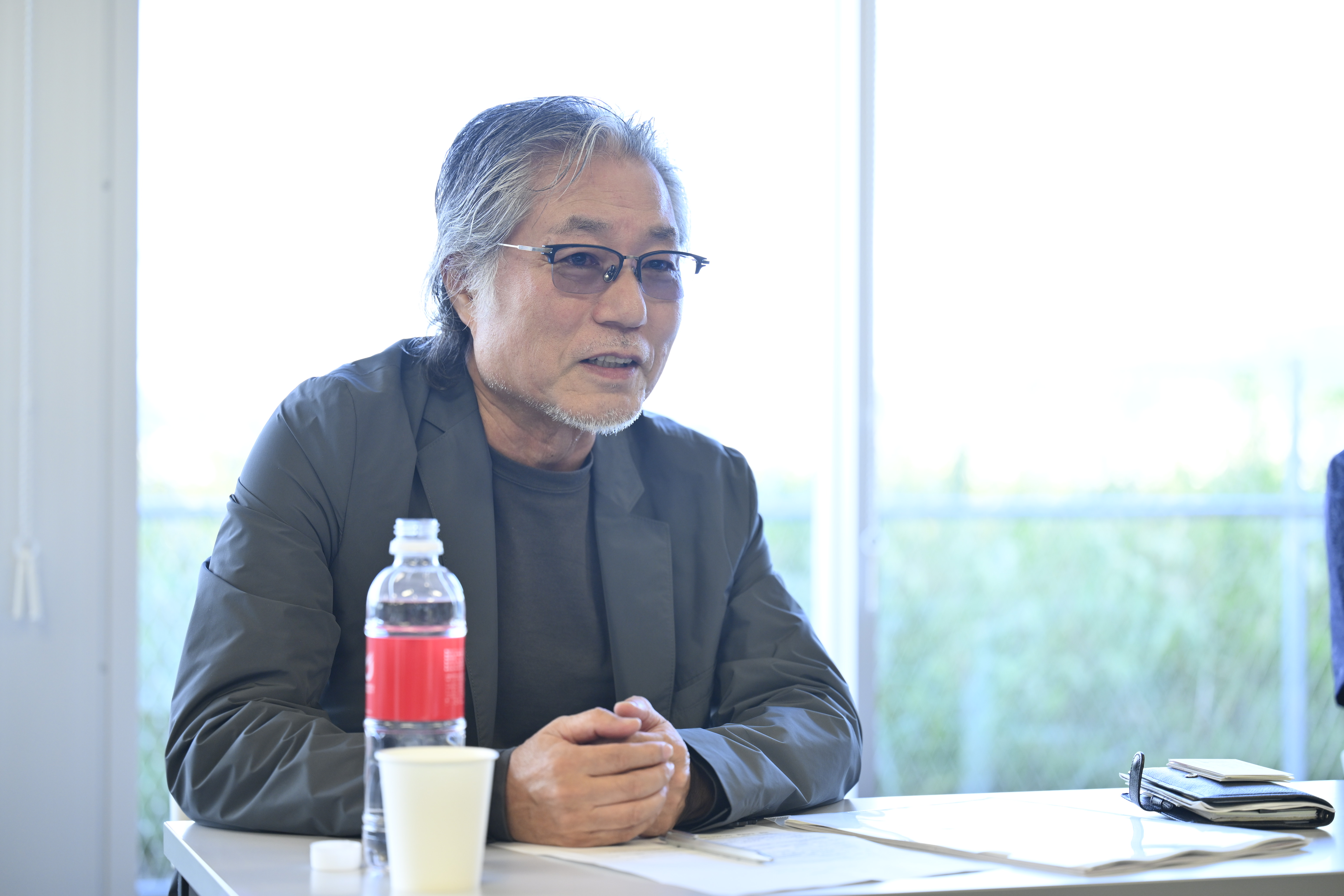
木原:社会に対して怒れる、何かしてやろうって思うことが大切なのかなと。僕はここの大学院で飲みながらでも社会に怒れる人たちに出会って、自分が変わったような気がしますから。
玉城:僕はあまり怒らないんですが、福祉や農業をしているんで制度に対して思うところはあります。怒りではなく、納得できないという感じですね。納得できないままにしておきたくないですが、そんなのばっかりなんですよ。農薬を使わないすごく非常識な農業をやっていると普通の農業やっている人からすれば非効率なことをやっているように見えることもあるんでしょうね。でも幸いなことに、僕はまわりには恵まれていまして。農業者ではなく福祉事業所で、かつ自然栽培なので制度に則るとか業務的な取引がないものの、村の農業委員会の会長を6年間もやらせてもらいました。

丹波:それは玉城さんのお人柄だと思いますよ。
-興味深いお話しをありがとうございました。最後に「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」に興味を持つ人に向けてメッセージをお願いします。
玉城:とにかく、いろんな経験をしてほしい。いろんなことに興味を持ってほしい。何でもいいです。頭の中にいっぱい選択肢がないと、何か一つやろうという発想が生まれないんですよ。他のことをたくさん知っていると、これとこれを合わせたらいいんじゃないかというアイデアも浮かんでくると思います。
住友:日本は虐げられている人にスポット当たってないんですよね。だからこそ理不尽な状況にいる人たちをどうにかしたいっていう気持ちで取り組んでほしいと思います。
木原:私情で怒るんじゃなくて、大義で怒ってほしい。でも怒りだけでは変な方向へ行ってしまうので、何かやりがいとか楽しいって感じることを見つけていくといいのではないかと思います。
丹波:私たちもパートナーとしてサポートしますので、一緒に社会課題を考えていきましょう。
深尾:憤りや怒りは本当に大事です。今の教育はプログラム化された予定調和型の学びになってしまっている。テストやレポートも先生が喜ぶ答えをよく知っているから、そういうものを返してくる。それでは何にもなりません。例えば、授業の一環で獣害被害を取り上げ、殺された動物たちの姿を学生たちに実際に見せたんですが、世の中そんなもんだ、仕方ないと考える学生と、命の問題として考える学生と、ふたつに分かれました。そんなもんだと納得させるのは「地球防衛軍」的発想なんですよ。反乱軍になって世の中を変えるには、感受性みたいなものが実はものすごく大事だし、それがないと、どこにもたどり着けません。先に話した議論する、物事を批判的に見るということに繋がりますが、憤る、怒ることを、人間として持っていてほしい。そして誰が困っているのか、誰が泣いているのかをきちんと理解した上で、どうすべきかを考えてほしいと思います。
もちろん私たちも大学のあり方、教育のあり方を変えなければならないと覚悟しています。自分たちの足りないところを自覚しつつ、京都文教大学、琉球大学との連携、そして皆さんのようなソーシャルイノベーターやそれを支える京都信用金庫などの企業とのパートナーシップで大学のソーシャル・イノベーションを起こし、未来のソーシャルイノベーターと思考していきたいと思います。

キックオフセミナー 登壇者座談会 【後編】
[ 2024.12.17 更新 ]
-2025年に開講する大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラムへの思いをお聞かせください。
深尾:龍谷大学は長期ビジョンの中で「社会変革の中核的担い手になる」と明言しています。つまり、社会変革のハブになる発想です。このような大学は日本中探しても類をみないと思います。自治体や企業なんかも巻き込んで展開する今回のプログラムは社会変革のハブになるために重要だと考えています。
丹波:龍谷大学大学院の政策学研究コースが、その役割を担っていたと思うんですけど、今回のプログラムによって政策学研究コースのウリが少なくなるのでは?と考えたりしています。
深尾:単体の大学院では教員の数も限られていますし、いろんな人たちと繋がらないとできないこともある。でも今回のプログラムのように、他の大学と連携するということでかなり広がっていくわけですよ。京都文教大学の心理学という強み、地域のいろんな矛盾の向き合い続ける琉球大学の強みを我々が共有することで、新たな何かを生み出し政策学研究科全体にフィードバックされていくと思います。ウリが少なくなるというより、今後自分たちがやりたい研究科の姿に歩みを進める上で非常に強い力になると思いますし、研究科自体の学びもバージョンアップするのではと期待しています。
木原:私は龍谷大学の大学院で学んだので、信頼度は高いのですが、ソーシャル・イノベーションを起こす力が、このプログラムで学ぶだけで本当に鍛えられるものなのか、これに関してはちょっと疑問を呈したいのですが、いかがでしょう。
深尾:プログラムの中で完成するというものでなくていいんですよ。現場や社会を知っている人が、何かヒントをもらう、教授陣をはじめいろんな知見がある中で自分のことを整理するきっかけになれば。このプログラムは単なる養成講座ではないと思うので、さまざまな人や課題に触れて、ものの見方や考え方に刺激を受けながら、一生をかけて思考していく人たちを増やしていきたいと思います。
木原:なるほど。私は大学時代、勉強そっちのけで小学校を回って温暖化の出前授業をやっていて、卒業後NPOの事務局長になったんですが、学ばないとまずいなと思って大学院に入ったんです。その中で社会に対して真剣に怒れる人や、海外で活動している人や、社会をなんとかするために人と組織を育てようと頑張っている人などいろんな人からいい刺激を受けました。
住友:現場を経験して学ぶのは全然違いますよ。それはすごくわかります。学生と違って、社会に出てから学ぶというのは本当に気持ちがあるんで、吸収力が違うでしょう。僕は23歳の時から雑誌づくりを始めましたけど、最初は全くの素人だった。だからあらゆる研修や勉強会に出ましたし、コンサルティングもお願いしました。決して安くはなかったですが、それをゼロにするか、ギャラを何倍にするかは自分次第なんですよ。それは大学も一緒ですね。お金を出して学んだことをどう使うかという。
玉城:僕は今、勉強したいなと思います。大学のときはほとんど勉強してなくて。社会人になって、こうやって通える場所があるのはうらやましい。ソーシャル・イノベーションのプログラムの中で実際にある社会課題についてみんなで一緒に考えていけけるのもいいと思います。いろんなものに触れる機会も多くなるでしょうし、自分が気づかなかったことにも気づくきっかけが学ぶことによって見つかるような気がします。自分から求めないと、というのはどこに行っても同じですが、そうさせてくれる環境があるというのはとてもいいと思います。
住友:こういうプログラムは教える側の立ち位置というか、基準がどこにあるかが大きく影響しますよね。
深尾:今までの大学教育の枠組みではできないという覚悟はあります。実は社会人も対象とした大学院をやっている時点で、多くの教員が感じていることなんですよ。実社会の中で課題や意識を持っている社会人に対して、浮世離れしたことだけ教えてもニーズに応えられず学生も来ません。だから既存の大学教員だけでは足りない部分は、自治体や企業とパートナーシップを組んでいきたいと思います。このプログラムはある意味、大学教員が問われる、刃が自分たちに向いてくる、むしろ向けながら取り組まなくてはいけないと一教員として考えています。
-ソーシャル・イノベーションを大学で教える、ソーシャルイノベーターを大学で育てるということは大変なことだということを理解しました。そのうえで龍谷大学としてどのようなことを学んでほしいと思いますか?
深尾:龍谷大学は市民社会と共に学んできた大学なんですね。仏教系の大学ということもあって、これまでも犯罪を犯した人たちの更生を一緒になって考えたり、市民運動やNPOの人たちに学びの機会を提供したりすることやってきました。今までの大学の役割とは違う、いろんな人たちが来てくれるこの環境は学部の教育や学生たちの教育に、ものすごく生きていると感じています。今回は大学院のプログラムなので、教えるのではなく一緒になって悩んだり、考えたりすることが求められる。我々が今、このプログラムで規定しているソーシャル・イノベーションが、いい意味でどんどん裏切られていってほしいですね。
住友:想定を超えてくるという期待ですね。ところで今の学生って議論します?
深尾:二極化していますね。受験戦争的な価値で入学した学生は議論が苦手ですが、実はそうじゃない学生が増えてきているんです。その背景にあるのは、高校までの学び方が変わってきたということ。これまで大学に来なかったような人たち、例えば不登校でフリースクールに通っていた子や通信制高校などのラインですね。そういう、今までと違う層の学生は、ものすごく感受性が豊かで、議論できる。そういう意味で非常に面白くなっています。僕は不登校をしている子は、ある意味イノベーターだと思っています。あの年で、身を挺して社会や学校に反抗しているわけですから。その反抗によって大人たちは初めて教育に問題があるのでは、と気づけるんですよね。彼らがレジスタンスとして戦った結果、学校にとらわれない学び方ができるようになった。これがソーシャル・イノベーションだとも思います。苦しんだ、いじめられた、ということを踏まえて、チャンスをもぎ取ってきた人を、すごいなって言ってあげられる社会や教育じゃないといけないなと思います。
住友:僕の知っているフリースクールの卒業生たちが現場で活躍し始めているんですけど、彼らは摩擦を嫌うんです。みんなケンカをしない、いい子なんです。僕がちょっときついこと言うと「昭和のじじいはきつすぎ」と思ってしまう。ちょっと壁に当たると絶対乗り越えられないって心配になるんですよね。だって世の中汚い輩がいっぱいいるじゃないですか。起業された方って必ずそういう人とぶち当たってきていると思うし、正面切ってケンカしないといけない。だから議論する経験を積むっていうことは大切だし、世の中にいるダークな連中に近づく必要はないけれども、そういう存在がいるということはやっぱり知るべきだと思います。それと、どんどん海外にも行ってほしいですね。
木原:社会に対して怒れる、何かしてやろうって思うことが大切なのかなと。僕はここの大学院で飲みながらでも社会に怒れる人たちに出会って、自分が変わったような気がしますから。
玉城:僕はあまり怒らないんですが、福祉や農業をしているんで制度に対して思うところはあります。怒りではなく、納得できないという感じですね。納得できないままにしておきたくないですが、そんなのばっかりなんですよ。農薬を使わないすごく非常識な農業をやっていると普通の農業やっている人からすれば非効率なことをやっているように見えることもあるんでしょうね。でも幸いなことに、僕はまわりには恵まれていまして。農業者ではなく福祉事業所で、かつ自然栽培なので制度に則るとか業務的な取引がないものの、村の農業委員会の会長を6年間もやらせてもらいました。
丹波:それは玉城さんのお人柄だと思いますよ。
-興味深いお話しをありがとうございました。最後に「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」に興味を持つ人に向けてメッセージをお願いします。
玉城:とにかく、いろんな経験をしてほしい。いろんなことに興味を持ってほしい。何でもいいです。頭の中にいっぱい選択肢がないと、何か一つやろうという発想が生まれないんですよ。他のことをたくさん知っていると、これとこれを合わせたらいいんじゃないかというアイデアも浮かんでくると思います。
住友:日本は虐げられている人にスポット当たってないんですよね。だからこそ理不尽な状況にいる人たちをどうにかしたいっていう気持ちで取り組んでほしいと思います。
木原:私情で怒るんじゃなくて、大義で怒ってほしい。でも怒りだけでは変な方向へ行ってしまうので、何かやりがいとか楽しいって感じることを見つけていくといいのではないかと思います。
丹波:私たちもパートナーとしてサポートしますので、一緒に社会課題を考えていきましょう。
深尾:憤りや怒りは本当に大事です。今の教育はプログラム化された予定調和型の学びになってしまっている。テストやレポートも先生が喜ぶ答えをよく知っているから、そういうものを返してくる。それでは何にもなりません。例えば、授業の一環で獣害被害を取り上げ、殺された動物たちの姿を学生たちに実際に見せたんですが、世の中そんなもんだ、仕方ないと考える学生と、命の問題として考える学生と、ふたつに分かれました。そんなもんだと納得させるのは「地球防衛軍」的発想なんですよ。反乱軍になって世の中を変えるには、感受性みたいなものが実はものすごく大事だし、それがないと、どこにもたどり着けません。先に話した議論する、物事を批判的に見るということに繋がりますが、憤る、怒ることを、人間として持っていてほしい。そして誰が困っているのか、誰が泣いているのかをきちんと理解した上で、どうすべきかを考えてほしいと思います。
もちろん私たちも大学のあり方、教育のあり方を変えなければならないと覚悟しています。自分たちの足りないところを自覚しつつ、京都文教大学、琉球大学との連携、そして皆さんのようなソーシャルイノベーターやそれを支える京都信用金庫などの企業とのパートナーシップで大学のソーシャル・イノベーションを起こし、未来のソーシャルイノベーターと思考していきたいと思います。