【前編】に続き、【後編】ではパネルディスカッションの模様をレポートします。
パネリスト
株式会社ソルファコミュニティ 代表取締役 玉城卓氏

たんたんエナジー株式会社 代表取締役社長 木原浩貴氏

京都信用金庫 専務理事 丹波寛志氏

琉球大学地域共創研究科 研究科長 本村真

モデレーター
龍谷大学政策学部教授 大石尚子

今回は私たちが育成していきたいと思っているソーシャル・イノベーターである2人の起業家様、企業としてソーシャル・イノベーターを支えておられる京都信用金庫様、連携大学のひとつである琉球大学地域共創研究科の研究科長にお話しを伺います。まず、起業家のお2人には現在の事業について、京都信用金庫様にはこれからの金融機関としての取り組み、本村研究科長には「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」への期待を伺いたいと思います。
〈木原さん〉
高校生のときに知った気候変動問題を何とかしたいと大学に進学しました。大学で学べば学ぶほどこの問題を解決したいという思いが強くなり、気候変動問題に関わるNPOで働き、その後、再生可能エネルギーを供給する電力会社を立ち上げました。現在は福知山に拠点を置いて、「丹波丹後と繋がる電気」をキャッチフレーズに事業を展開し、すでに福知山の小・中学校は全て再生可能エネルギー100%の電気で学んでもらっています。
また、地域の金融機関からの借り入れと市民出資で中学校等の屋根に太陽光発電所や蓄電池を設置し、売電収入を地域の金融機関への返済や出資者への分配に充てるという、地域のお金で再生可能エネルギーを運用・還元していく仕組みをつくりました。出資者には投資家特典として、福知山の観光クーポンや特産品をプレゼントし、関係人口の創出強化にも繋げています。エネルギー事業を通じた繋がりのために、個人のご家庭にも電気を販売し、その売り上げの一部で子ども食堂の支援をおこなったり、子どもたちたちのスポーツ活動をサポートする団体のスポーンサーになったり、地域活動の支援に活用しています。
〈玉城さん〉
僕は農業と障がい者の就労支援という福祉を連携させて地域社会を築いていくことをメインに行っています。農業は、農薬や化学肥料だけでなく有機肥料も使わず、野菜や果実を作る「自然循環農法」という、ちょっと変わった方法に取り組んでいます。今、試行錯誤しながら挑戦しているのは、アイスクリームやシュークリームなどに使われるバニラビーンズの栽培です。バニラビーンズは、暑い国の植物なので露地でできるのは沖縄が限界。本土ではハウスでしか栽培できません。沖縄でバニラビーンズを作って販売までしている方もおり、高価格で取引されていると聞いていますが、安定的な生産はまだまだのようです。自然循環農法で質のいいバニラビーンズの栽培に成功し、安定して生産できるようになれば、障がいのある方や社会的就労が困難と言われている方が継続して就労できる仕事の場になるのではと期待しています。
〈丹波さん〉
京都信用金庫は、1971年に全国で初めて「コミュニティ・バンク」と宣言し、2023年には創立100周年を迎えさせていただきました。
今、時代は成長型社会から、成熟した社会、もっと言えば課題解決の社会へと展開しています。パラダイムシフトが起り、先行きが見通せない非常に難しい時代に突入している中で、金融の仕事は従来の決済機能だけでなく、課題解決といった機能が生命線になっていくと考えています。
このような背景を踏まえ、当行では経済的にも人口的にもダウンサイジングしている地域をもう一度リバイバルする試みとして、課題解決型店舗をスタートしました。職員は若手のみで、午前中だけ店舗を開け、お昼からは職員全員で地域をまわり、課題解決に取り組んでいます。おかげさまで、地域の方々より好評をいただき、現在は21店舗が課題解決型店舗、そして来年の1月には全店舗の半分ぐらいの47店舗が課題解決型店舗となる予定です。さらに課題解決を可視化・具現化できる場として2020年11月に河原町御池に「QUESTION」をオープンし、2022年5月には梅小路エリアに「QUESTION 梅小路」をオープンしました。そして先日、龍谷大学様、大阪ガス都市開発様とともに「共創HUB京都コンソーシアム」を組織し、2027年に京都市立芸術大学新キャンパスの隣接地に「共創HUB京都」のオープンを予定しています。こちらは8階建てのビルで、社会課題の解決につながる産業の創出、コミュニティの形成、人材の育成ができる場を目指しています。
〈本村先生〉
2022年創設と、地域共創研究科ができて数年しか経っていない段階でこのプログラムにお声掛けいただいたのはとても光栄です。本事業は理系の大学院では何十年も前からやっている連携を、文系の大学院同士でやってみるという文部科学省の新しい試みです。しかも私立大学である龍谷大学がハブとなり、そして臨床心理で伝統がある京都文教大学も入り、かつ国立でエリアが違う沖縄の琉球大学が入るという点も非常にユニークです。先ほど入澤学長がお話しされたように、地域間の連携を生かしながら日本全体にも関わるさまざまな課題を解決するための仕組みをつくることで、ソーシャル・イノベーション人材が育っていくのではないかと構想しています。
起業家のお2人は起業を成功させるうえで大切なものは何だと思われますか。
〈木原さん〉
龍谷大学政策学研究科で修士課程を学んでいたのですが、そこで出会った、日本や海外のエネルギー問題に高い知見を持つ研究者の方々と一緒に研究させていただきました。私は先頭に立つタイプではないのですが、グループでの研究の中でブレない立ち位置というものを自分自身に見い出せたこと、先生をはじめ仲間からの非常に力強い後押しがあったことが起業という一歩踏み出すきっかけになったと思います。
コロナ禍の世界的な影響で天然ガスが日本に届かず、仕入れ価格が急上昇し経営危機に陥ったこともありましたが、「一緒に乗り越えましょう」と言ってくださった京都北都信用金庫の融資や、取り組みに賛同してくださったファンドの投資のおかげで、乗り切ることができました。改めて人との繋がりというものがいちばん大きいと思っています。
〈玉城さん〉
福祉=高齢者というイメージしかなかったので、まず高齢者福祉の仕事に就いたのですが、経営者と意見の違いなどがあり退職しました。その後、いくつかの福祉現場で働きましたが、何か自分でやった方がいいなと思うようになり、キャリアの中でもっともやりがいを感じた障がい者の就労支援と農業を融合させた事業を立ち上げました。起業してからは、大変だったことが思いつかないほど、まわりの人たちに恵まれ、12年前に起業したときの仲間たちは1人も辞めることなく一緒に仕事をしています。今回もこのような場に呼んでいただけましたし、改めて自分は恵まれているなと実感しています。頭を悩ませることがあるとすれば、資金繰りということだけです。
この話を受けて、起業家を支える京都信用金庫様としてはいかがですか。
〈丹波さん〉
京都信用金庫では、金融包摂に積極的に取り組んでいます。特に経営支援を必要としているお客さまへの支援のほか、事業の実績はないけれども夢や企画を持っておられる起業家の創業支援も積極的におこなっています。例えば、地域や社会の課題をビジネスによって解決することを目指されている起業家を応援する『京信・地域の起業家アワード』を11回開催し表彰をしてきました。
さらに木原さんが融資を受けられた京都北都信用金庫様、滋賀の湖東信用金庫様、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター様と協定を結び、社会課題を解決しながらESG経営を目指す企業を、経営方針や事業計画、事業内容、社会的インパクトなどを基準として認証する「ソーシャル企業認証制度」も設けました。現在は六つの近畿エリアの信用金庫が力を合わせて、1200ほどの企業を認証し、支援しています。
本村先生にご質問します。民間でもイノベーション/インキュベーションのプログラムを提供しています。アカデミックな大学院研究科としてのソーシャル・イノベーション人材育成プログラムとの違いはどこにあるとお考えですか?
〈本村先生〉
社会や企業が直面している課題解決に取り組むために必要な力を、アカデミックなベースで学ぶことで、ソーシャル・イノベーション人材としてスキルを積み上げていくための土台がしっかりできることが違いです。またアカデミックな領域でさまざまな知見を深めている教員たちと深く関わり、ネットワークが構築できる点も、社会を変える人材を育成するための大きな強みになると思っています。
ソーシャル・イノベーション人材として活躍するには、木原さんや玉城さんがおっしゃるように、仲間や人とのつながりが重要です。「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」では、実学的な学びの中でさまざま人と出会えますし、「大学だったら協力しますよ」という大学の信用度をベースにしてネットワークを広げることもできます。資金的なことは事業をやる上で必要ですけれども、このプログラムでは、それを超えた自分としての立ち位置、今後30年、40年、社会にどう関わっていくのかを深く探るためのプラットフォームづくりを考えています。
最後に「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」への期待をお聞かせください
〈木原さん〉
ソーシャル・イノベーション人材は果たして養成しうるものなのかとちょっと疑問を持ったのですが、もし私にソーシャル・イノベーション人材としての要素があると思っていただけるのならば、養成可能だと思います。私は大学在学中に「自分たちが社会を良くするために必要なんだと思って学びなさい」と言われたのですが、それって単に理念だけではなく、ワークショップの運営の仕方、ホームページの立ち上げ、出版物を自分でDTPデザインするなどの社会活動のために必要なスキルも含めての話でした。
社会を変えるときに必要なのは何も大きなことをやるだけではない。例えばウチの会社では金融機関に勤務経験のある社員が電気の売り買いなど私にはできないことをやってくれています。会社というのはいろんなスキルを持った人が集まって動かしているんです。
ぜひ「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」ではマインドを養成するとともに、このプログラムで身につけられるさまざまなスキルはこういうことで役に立つということを、具体的に示していただきたいと思います。そして社会は変えられるという実感を自分自身で得た教員や実務家の方から教えていただきたい。私自身、実際に社会を変えた方に出会えたおかげで、自分も社会を変えられるんだと本気で思えるようになりました。
〈玉城さん〉
僕が一緒に働いていて、一番すごいと思う人は、バランス感覚が良い人です。人と人、人と仕事、仕事と仕事などいろんなバランスが取れる人は、どこにいっても活躍できると思います。僕は実践で身につけたことばかりなので、基礎がない。基礎がないとやはり苦労する部分もあります。先生の話を伺い、「ソーシャル・イノベーション人材養成講座」では基礎を築いた上で、実践力を身につけられるのがすごくうらやましい。また学生という立場や本村先生がおっしゃった大学間の連携をうまく使って、いろんな人に会いに行ったり、いろんなことを見に行ったりできるのもすごくいい。プログラムのメリットをうまく使って、バランス感覚を磨いていってほしいですね。
〈丹波さん〉
京都信用金庫では、人材の育成に関しまして、職員同士のコミュニケーションが豊かで風通しのいい職場風土を目指す『対話型経営』、組織をフラット化させ、意見を言いやすい環境を作る『分散型組織』、これらを土台として自らが仮説を立て実践を重ねる中で自らの成長を実感できる『自律型人材の育成』ができると考えています。具体的には、2020年11月、膳所支店を若手職員のみで構成された課題解決型店舗としてオープンしました。課題解決型店舗は現在21店舗まで増えています。当金庫では、仕事の仕方を金融のルーチン業務を8割に抑え、お客さまや地域の課題解決にかかる企画の仕事を2割にしています。職員は地元の商店などをめぐってお悩みをお聞きし、店舗ではみんなで解決方法を考えます。お客さまに感謝されると人事評価が上がるという仕組みです。そして、課題解決を実践できる人材育成にはチームワーク、フィールドワーク、プレゼンテーションが鍵になると考え実践をしています」。
〈本村先生〉
ソーシャル・イノベーションの最前線に立つ皆さんに、この「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」について共感いただいたことを改めて感謝します。先ほども申したように大学がやるんだったらということで、いろいろと協力してくれるステークホルダーが今後どんどん増えていくことでしょう。
玉城さんから「バランスが大切」という話がありましたが、そのバランスをとる一つの柱となりうる臨床心理に強い京都文教大学が入っているこのプログラムは、ソーシャル・イノベーション人材を育成する仕組みとして強みを有すると思います。
京都の課題、沖縄の課題を行ったり来たりしながら、日本全体、場合によっては海外に展開するような社会課題を解決し、新しい何かを生み出すために必要な力と仲間を得てほしいですね。

閉会の挨拶
京都文教大学臨床心理学研究科 研究科長 濱野清志
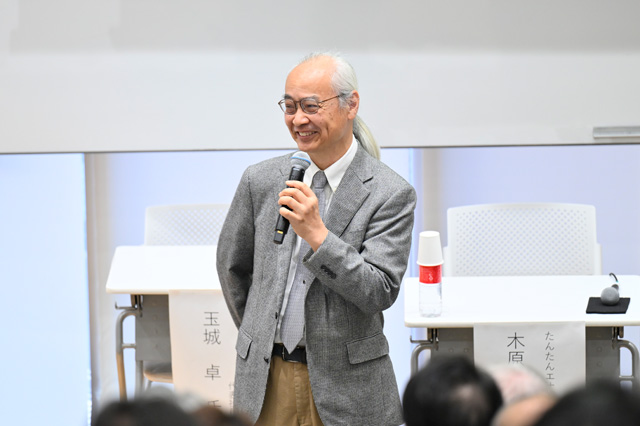
「ソーシャル・イノベーション」という社会を変革していく力を養成するプログラムをつくるというのは、大変な課題でした。私はソーシャル・イノベーション人材を養成するプログラムとは当たり前のことを勉強して当たり前になるのではなく、何かわからないけども自分が感じることを真剣に内側で熟成してバーンと爆発させる、そのきっかけとなるようなものだと考えています。
ぜひ関心を持ってきていただき、多くの方に受講してもらえればと思います。
2024年10月12日「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」
キックオフセミナー【後編】
[ 2024.12.24 更新 ]
【前編】に続き、【後編】ではパネルディスカッションの模様をレポートします。
パネリスト
株式会社ソルファコミュニティ 代表取締役 玉城卓氏
たんたんエナジー株式会社 代表取締役社長 木原浩貴氏
京都信用金庫 専務理事 丹波寛志氏
琉球大学地域共創研究科 研究科長 本村真
モデレーター
龍谷大学政策学部教授 大石尚子
今回は私たちが育成していきたいと思っているソーシャル・イノベーターである2人の起業家様、企業としてソーシャル・イノベーターを支えておられる京都信用金庫様、連携大学のひとつである琉球大学地域共創研究科の研究科長にお話しを伺います。まず、起業家のお2人には現在の事業について、京都信用金庫様にはこれからの金融機関としての取り組み、本村研究科長には「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」への期待を伺いたいと思います。
〈木原さん〉
高校生のときに知った気候変動問題を何とかしたいと大学に進学しました。大学で学べば学ぶほどこの問題を解決したいという思いが強くなり、気候変動問題に関わるNPOで働き、その後、再生可能エネルギーを供給する電力会社を立ち上げました。現在は福知山に拠点を置いて、「丹波丹後と繋がる電気」をキャッチフレーズに事業を展開し、すでに福知山の小・中学校は全て再生可能エネルギー100%の電気で学んでもらっています。
また、地域の金融機関からの借り入れと市民出資で中学校等の屋根に太陽光発電所や蓄電池を設置し、売電収入を地域の金融機関への返済や出資者への分配に充てるという、地域のお金で再生可能エネルギーを運用・還元していく仕組みをつくりました。出資者には投資家特典として、福知山の観光クーポンや特産品をプレゼントし、関係人口の創出強化にも繋げています。エネルギー事業を通じた繋がりのために、個人のご家庭にも電気を販売し、その売り上げの一部で子ども食堂の支援をおこなったり、子どもたちたちのスポーツ活動をサポートする団体のスポーンサーになったり、地域活動の支援に活用しています。
〈玉城さん〉
僕は農業と障がい者の就労支援という福祉を連携させて地域社会を築いていくことをメインに行っています。農業は、農薬や化学肥料だけでなく有機肥料も使わず、野菜や果実を作る「自然循環農法」という、ちょっと変わった方法に取り組んでいます。今、試行錯誤しながら挑戦しているのは、アイスクリームやシュークリームなどに使われるバニラビーンズの栽培です。バニラビーンズは、暑い国の植物なので露地でできるのは沖縄が限界。本土ではハウスでしか栽培できません。沖縄でバニラビーンズを作って販売までしている方もおり、高価格で取引されていると聞いていますが、安定的な生産はまだまだのようです。自然循環農法で質のいいバニラビーンズの栽培に成功し、安定して生産できるようになれば、障がいのある方や社会的就労が困難と言われている方が継続して就労できる仕事の場になるのではと期待しています。
〈丹波さん〉
京都信用金庫は、1971年に全国で初めて「コミュニティ・バンク」と宣言し、2023年には創立100周年を迎えさせていただきました。
今、時代は成長型社会から、成熟した社会、もっと言えば課題解決の社会へと展開しています。パラダイムシフトが起り、先行きが見通せない非常に難しい時代に突入している中で、金融の仕事は従来の決済機能だけでなく、課題解決といった機能が生命線になっていくと考えています。
このような背景を踏まえ、当行では経済的にも人口的にもダウンサイジングしている地域をもう一度リバイバルする試みとして、課題解決型店舗をスタートしました。職員は若手のみで、午前中だけ店舗を開け、お昼からは職員全員で地域をまわり、課題解決に取り組んでいます。おかげさまで、地域の方々より好評をいただき、現在は21店舗が課題解決型店舗、そして来年の1月には全店舗の半分ぐらいの47店舗が課題解決型店舗となる予定です。さらに課題解決を可視化・具現化できる場として2020年11月に河原町御池に「QUESTION」をオープンし、2022年5月には梅小路エリアに「QUESTION 梅小路」をオープンしました。そして先日、龍谷大学様、大阪ガス都市開発様とともに「共創HUB京都コンソーシアム」を組織し、2027年に京都市立芸術大学新キャンパスの隣接地に「共創HUB京都」のオープンを予定しています。こちらは8階建てのビルで、社会課題の解決につながる産業の創出、コミュニティの形成、人材の育成ができる場を目指しています。
〈本村先生〉
2022年創設と、地域共創研究科ができて数年しか経っていない段階でこのプログラムにお声掛けいただいたのはとても光栄です。本事業は理系の大学院では何十年も前からやっている連携を、文系の大学院同士でやってみるという文部科学省の新しい試みです。しかも私立大学である龍谷大学がハブとなり、そして臨床心理で伝統がある京都文教大学も入り、かつ国立でエリアが違う沖縄の琉球大学が入るという点も非常にユニークです。先ほど入澤学長がお話しされたように、地域間の連携を生かしながら日本全体にも関わるさまざまな課題を解決するための仕組みをつくることで、ソーシャル・イノベーション人材が育っていくのではないかと構想しています。
起業家のお2人は起業を成功させるうえで大切なものは何だと思われますか。
〈木原さん〉
龍谷大学政策学研究科で修士課程を学んでいたのですが、そこで出会った、日本や海外のエネルギー問題に高い知見を持つ研究者の方々と一緒に研究させていただきました。私は先頭に立つタイプではないのですが、グループでの研究の中でブレない立ち位置というものを自分自身に見い出せたこと、先生をはじめ仲間からの非常に力強い後押しがあったことが起業という一歩踏み出すきっかけになったと思います。
コロナ禍の世界的な影響で天然ガスが日本に届かず、仕入れ価格が急上昇し経営危機に陥ったこともありましたが、「一緒に乗り越えましょう」と言ってくださった京都北都信用金庫の融資や、取り組みに賛同してくださったファンドの投資のおかげで、乗り切ることができました。改めて人との繋がりというものがいちばん大きいと思っています。
〈玉城さん〉
福祉=高齢者というイメージしかなかったので、まず高齢者福祉の仕事に就いたのですが、経営者と意見の違いなどがあり退職しました。その後、いくつかの福祉現場で働きましたが、何か自分でやった方がいいなと思うようになり、キャリアの中でもっともやりがいを感じた障がい者の就労支援と農業を融合させた事業を立ち上げました。起業してからは、大変だったことが思いつかないほど、まわりの人たちに恵まれ、12年前に起業したときの仲間たちは1人も辞めることなく一緒に仕事をしています。今回もこのような場に呼んでいただけましたし、改めて自分は恵まれているなと実感しています。頭を悩ませることがあるとすれば、資金繰りということだけです。
この話を受けて、起業家を支える京都信用金庫様としてはいかがですか。
〈丹波さん〉
京都信用金庫では、金融包摂に積極的に取り組んでいます。特に経営支援を必要としているお客さまへの支援のほか、事業の実績はないけれども夢や企画を持っておられる起業家の創業支援も積極的におこなっています。例えば、地域や社会の課題をビジネスによって解決することを目指されている起業家を応援する『京信・地域の起業家アワード』を11回開催し表彰をしてきました。
さらに木原さんが融資を受けられた京都北都信用金庫様、滋賀の湖東信用金庫様、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター様と協定を結び、社会課題を解決しながらESG経営を目指す企業を、経営方針や事業計画、事業内容、社会的インパクトなどを基準として認証する「ソーシャル企業認証制度」も設けました。現在は六つの近畿エリアの信用金庫が力を合わせて、1200ほどの企業を認証し、支援しています。
本村先生にご質問します。民間でもイノベーション/インキュベーションのプログラムを提供しています。アカデミックな大学院研究科としてのソーシャル・イノベーション人材育成プログラムとの違いはどこにあるとお考えですか?
〈本村先生〉
社会や企業が直面している課題解決に取り組むために必要な力を、アカデミックなベースで学ぶことで、ソーシャル・イノベーション人材としてスキルを積み上げていくための土台がしっかりできることが違いです。またアカデミックな領域でさまざまな知見を深めている教員たちと深く関わり、ネットワークが構築できる点も、社会を変える人材を育成するための大きな強みになると思っています。
ソーシャル・イノベーション人材として活躍するには、木原さんや玉城さんがおっしゃるように、仲間や人とのつながりが重要です。「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」では、実学的な学びの中でさまざま人と出会えますし、「大学だったら協力しますよ」という大学の信用度をベースにしてネットワークを広げることもできます。資金的なことは事業をやる上で必要ですけれども、このプログラムでは、それを超えた自分としての立ち位置、今後30年、40年、社会にどう関わっていくのかを深く探るためのプラットフォームづくりを考えています。
最後に「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」への期待をお聞かせください
〈木原さん〉
ソーシャル・イノベーション人材は果たして養成しうるものなのかとちょっと疑問を持ったのですが、もし私にソーシャル・イノベーション人材としての要素があると思っていただけるのならば、養成可能だと思います。私は大学在学中に「自分たちが社会を良くするために必要なんだと思って学びなさい」と言われたのですが、それって単に理念だけではなく、ワークショップの運営の仕方、ホームページの立ち上げ、出版物を自分でDTPデザインするなどの社会活動のために必要なスキルも含めての話でした。
社会を変えるときに必要なのは何も大きなことをやるだけではない。例えばウチの会社では金融機関に勤務経験のある社員が電気の売り買いなど私にはできないことをやってくれています。会社というのはいろんなスキルを持った人が集まって動かしているんです。
ぜひ「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」ではマインドを養成するとともに、このプログラムで身につけられるさまざまなスキルはこういうことで役に立つということを、具体的に示していただきたいと思います。そして社会は変えられるという実感を自分自身で得た教員や実務家の方から教えていただきたい。私自身、実際に社会を変えた方に出会えたおかげで、自分も社会を変えられるんだと本気で思えるようになりました。
〈玉城さん〉
僕が一緒に働いていて、一番すごいと思う人は、バランス感覚が良い人です。人と人、人と仕事、仕事と仕事などいろんなバランスが取れる人は、どこにいっても活躍できると思います。僕は実践で身につけたことばかりなので、基礎がない。基礎がないとやはり苦労する部分もあります。先生の話を伺い、「ソーシャル・イノベーション人材養成講座」では基礎を築いた上で、実践力を身につけられるのがすごくうらやましい。また学生という立場や本村先生がおっしゃった大学間の連携をうまく使って、いろんな人に会いに行ったり、いろんなことを見に行ったりできるのもすごくいい。プログラムのメリットをうまく使って、バランス感覚を磨いていってほしいですね。
〈丹波さん〉
京都信用金庫では、人材の育成に関しまして、職員同士のコミュニケーションが豊かで風通しのいい職場風土を目指す『対話型経営』、組織をフラット化させ、意見を言いやすい環境を作る『分散型組織』、これらを土台として自らが仮説を立て実践を重ねる中で自らの成長を実感できる『自律型人材の育成』ができると考えています。具体的には、2020年11月、膳所支店を若手職員のみで構成された課題解決型店舗としてオープンしました。課題解決型店舗は現在21店舗まで増えています。当金庫では、仕事の仕方を金融のルーチン業務を8割に抑え、お客さまや地域の課題解決にかかる企画の仕事を2割にしています。職員は地元の商店などをめぐってお悩みをお聞きし、店舗ではみんなで解決方法を考えます。お客さまに感謝されると人事評価が上がるという仕組みです。そして、課題解決を実践できる人材育成にはチームワーク、フィールドワーク、プレゼンテーションが鍵になると考え実践をしています」。
〈本村先生〉
ソーシャル・イノベーションの最前線に立つ皆さんに、この「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」について共感いただいたことを改めて感謝します。先ほども申したように大学がやるんだったらということで、いろいろと協力してくれるステークホルダーが今後どんどん増えていくことでしょう。
玉城さんから「バランスが大切」という話がありましたが、そのバランスをとる一つの柱となりうる臨床心理に強い京都文教大学が入っているこのプログラムは、ソーシャル・イノベーション人材を育成する仕組みとして強みを有すると思います。
京都の課題、沖縄の課題を行ったり来たりしながら、日本全体、場合によっては海外に展開するような社会課題を解決し、新しい何かを生み出すために必要な力と仲間を得てほしいですね。
閉会の挨拶
京都文教大学臨床心理学研究科 研究科長 濱野清志
「ソーシャル・イノベーション」という社会を変革していく力を養成するプログラムをつくるというのは、大変な課題でした。私はソーシャル・イノベーション人材を養成するプログラムとは当たり前のことを勉強して当たり前になるのではなく、何かわからないけども自分が感じることを真剣に内側で熟成してバーンと爆発させる、そのきっかけとなるようなものだと考えています。
ぜひ関心を持ってきていただき、多くの方に受講してもらえればと思います。