龍谷大学 学長 入澤 崇 開会挨拶

龍谷大学は、いよいよ新しい一歩を踏み出します。この度、沖縄の琉球大学、京都文教大学と連携をして社会課題に向き合い、社会課題を解決しようとする志の高い人材を育成する新しい教育プログラム「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」を開設します。このプログラムは、深刻かつ複雑化する社会課題に向き合い、それを解決しようとする人を育成するという、大学を挙げてのプロジェクトです。
龍谷大学は数年後、京都駅前東側に金融界(京都信用金庫)、産業界(大阪ガス都市開発)とスクラムを組み、社会人そして学生たちが一緒になって、深刻な社会課題を解決する人たちを育成する施設を建設します。今回の養成プログラムに通底するものです。
これからの時代は「共創」です。では何を創るのか。よりよい社会です。これからの未来を創るのは本日来場してくださっているみなさんです。今回の養成プログラムに参加してもらい、充実した学びの時間を過ごしてもらえたらと切に願っております。
ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム 概要説明
龍谷大学政策学研究科長 中森孝文

顕在化していない社会課題から新しい価値を生み出すために
ソーシャル・イノベーションという言葉は、いろんな意味を持って広まっているので、まず私たちが考えるソーシャル・イノベーションとは何かを整理します。
私たちは、タイパやコスパという言葉で表されるような、できるだけ少ない資金で、できるだけ早くできるだけ多くの富を得る経済合理性が好きです。経済合理性を追求すると、新しい技術、新しいモノ、新しい産業、新しい仕組みが生まれ便利になります。しかし便利な社会を追求したが故の弊害も生み出されます。環境への負担もそうですが、給料が良く便利な地域で住みたいという人が増え、過疎問題が生じたり、自分たちさえよければという総取りみたいな考え方になり経済格差を生み出したりします。私たちが取り組む今回のプログラムは、便利で非常に良い社会構造のメリットを享受できない人びとが、直面している困難さを社会課題としてとらえます。そして社会課題から、新しいポテンシャルの芽を見つけて、今までになかったような新しい価値を見出し、社会変革できる力を受講生の皆さんに身につけてもらおうとするものです。
社会課題は行政に解決してもらえばいいという人もいるかもしれません。しかし、社会課題が多様化している今は、一つの自治体や一つの国ではなかなか解決できません。しかも日本は国も自治体も強烈な財政赤字ですから、行政に委ねていては解決できない社会課題が山積しています。そこで必要となるのが、社会課題を多面的な側面から眺め、そこから新しいポテンシャルの芽を見つけ出し、それらを使って今までになかったような新しい価値を生んでいくようなイノベーティブな発想で解決できる人たちなのです。
3大学連携によって多角的な視点と実行力を養う
今回なぜ3大学が連携するに至ったのかというと、多様な社会課題を解決するには、多様な知見はもちろん多様なものの見方が必要だからです。「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」は、ソーシャル・イノベーションとは何かを理解したうえで、3大学から提供される人文・社会科学系科目によって、多様な社会課題に対応できる知識やスキル、多角的な見方など、社会課題解決に必要な基礎的な素養を身につけます。
教育プログラムの仕上げとなるキャップストーン・プログラムは3大学が一緒になり、地域にある社会課題を事例として取り上げて、実際に解決策を考えていきます。沖縄の課題、京都の課題、様々な課題の存在を知り、多面的な視点から課題に向き合い、持続的な解決に向けたビジネスプランなどの計画を立て、必要なプロセスをデザインしていきます。途中、社会課題を提供してくださる関係機関からの評価を受けながら、受講生のアイデアの質を高めていくことで、社会的にインパクトの高い活動をしていく力を身につけていただきたいと思っています。
ソーシャルイノベーターとして社会で認められる制度を確立
もう一つは認証制度です。ヨーロッパはいろいろな国があるため、同じ名称の修士号という学位であっても、国によって学位の能力が違っていることもあります。そこでヨーロッパのどこに行っても、その力を持っているということを証明する制度(EQF)を設けています。それを応用し、琉球大学を修了した人も京都文教大学を修了した人も龍谷大学を修了した人も、修士号という学位だけでなく、ソーシャル・イノベーションの人材だと証明できる資格をつくろうと考えています。
昨今は、企業や団体などに所属する社員や職員をはじめ、社会人の学び直しの機運が高まっているので、オンラインの科目も充実させ、夜間や土曜日にも受講できるような体制をつくってまいります。龍谷大学政策研究科では1年で修士号を取得できる制度もあります。ぜひ、さまざまな知識やスキル、多面的な見方といった知見を大学院で習得していただき、それらの知見を用いて社会課題の解決につなげていっていただきたいと思います。
講演 「社会課題解決に向けた新たな価値創造」
株式会社とくし丸 取締役 住友達也氏
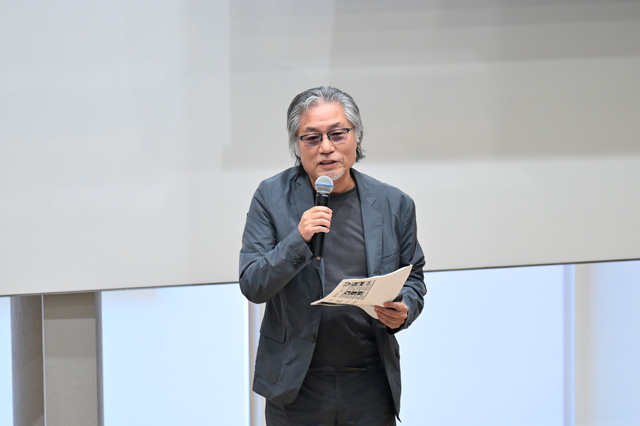
買い物難民という社会課題を解決するビジネスモデルを構築
僕は23歳で資金も経験もキャリアも人脈も何にもないからところから出版社を立ち上げ、経常利益毎年10%以上という会社に育て上げました。1000社起業して残るのは数社というなかで、なぜ生き残れたのかというと、真面目に一生懸命頑張るのは当たり前として、雑誌や広告業界などメディアが非常に伸びていた時代に乗っかったんだろうと思います。46歳のとき、得意でなかった組織運営や経営は人に任せて、出版社を退職し、その後の人生を楽しんでいました。移動スーパーを始めようと思ったのは、高齢の母が「買い物難民」になっているという事実に直面したからです。高齢者人口は増える一方なのに、それを支える若い世代は減っていく。今後、困った高齢者の数は、ますます増えていくことになる。この市場は伸びると思いました。
移動スーパー「とくし丸」の販売員はすべて個人事業主です。僕らはプロデューサー的な立場で「とくし丸」というブランドをつくり、地域のスーパーと契約。個人事業主となった販売員はそのスーパーと契約し、商品を借り受けて販売します。
現在、全国140社のスーパーと提携し、1200台の移動スーパー「とくし丸」が走っています。1台あたり150人ぐらいの顧客がいるので、毎日17万人ぐらいのお客さんの元に通っていることになります。
大切なのは困っている人を何とかしたい気持ち
先日「IT企業を成功させました。僕は勝ち組です」という若手の経営者の方が東京から徳島までわざわざ来てくれました。とても賢く、性格も良く、育ちのいい若者なのです。ただ、話を聞いていると、彼らは弱者や困っている人たちのためではなく、自分の半径3キロから5キロの範囲で、綺麗ごとを言いながら、かっこいい事業でお金を集められればいいと思っていると感じたんです。僕はそうはなりたくない。こういった人たちは企業をそこそこ成功させると思うんですけれど、企業というのは5年、10年、30年、その先まで適正な利益を上げながら継続できる仕組みをつくるってことがとても重要なんです。
僕は綺麗ごとではなく、「儲けはお布施」のようなものだと思っています。出版社も「とくし丸」も、お金儲けをしようと思って始めていません。やりたいと思ったことをやって、それが誰かに喜ばれたり、ありがとうって感謝されたりして、その結果としてお布施のようにお金が回ってくる。その仕組みをつくりたいって本気で思っているんです。
食べる楽しみを届けるだけでなく、高齢者の見守りの隊として
「とくし丸」は命を守るための役割も担っています。まず一つは「食」です。「とくし丸」を始めたばかりの頃は、僕自身が販売員となって、高齢者宅を訪問していました。そこで、「移動手段がなく、タクシーに乗って病院に行くときだけしかスーパーに行けない」「足腰が悪いのでご近所さんが1日1回持ってきてくれるお弁当を3回に分けて食べている」など、泣きそうになるような生活をされている方にたくさん出会ったんです。こういう人たちに単なる食べものではなく、新鮮で美味しい食べものを届け、食を楽しむ気持ちを生きる力にしてもらいたいと思っています。
もう一つは「見守り」です。「とくし丸」は対面販売なので、必ず生存確認ができます。実際「いつものおばあちゃんが来ない」と、民生委員さんに電話したら家の中で倒れていたということもあります。こういう話を聞きつけて、ビジネスにしましょう、見守り機器を一緒に販売しましょうと、持ちかけてくる事業所があるんですが、僕はいつもお断りしています。お客さんが調子悪かったり、倒れていたりしていたら、通報するのは人として当たり前であって、自分の大事なお客さんを見守りの代償としてお金に変換するのは違う。多分ビジネスにはなるんでしょうけれども、そこをビジネスにしてはいけない気持ちがとてもある。いつも顔を合わせるおばあちゃんからちょっと調子悪いって聞くと、病院行こうよって言いますよね。ただそれだけ。威張るようなことでもなくて、当たり前なことですから。
生きる楽しみづくりの一環として高齢者向け情報誌を創刊
先ほど申しあげたとおり、僕は会社の経営が得意ではないので、「とくし丸」が軌道に乗ったのを機にM&Aで上場会社に売却しま した。そのタイミングで手を引くつもりだったのですが、「あなた雑誌をつくりたいんでしょう」と、新たな経営元から持ちかけられ、80代前後の方をターゲットにした雑誌『ぐ〜す〜月刊とくし丸』を創刊しました。「とくし丸」の車両と提携スーパーの店頭のみの販売なので、実際のところまだ全然売れていません。でも、『ぐ〜す〜月刊とくし丸』に投稿が掲載された90歳のおばあちゃんから「投稿が載ったのがうれしくて、まだしばらく頑張って生きようと思います」という編集者冥利に尽きるお便りが届いたんです。こんなに喜んでくれる、生きがいになるっていう、お便りがもらえる雑誌の編集者ってなんて、幸せなんだろうって。
創刊から1年間で数千万の赤字のですが、この雑誌は高齢者たちに必ず爆発的にヒットします。1冊280円。この低価格でも5万部以上売れると儲かるんです。まずは「毎回楽しみに読んでいます」という5万人以上の人たちを僕はつくっていく。さらにそれが10万20万人になれば、本業の移動スーパーに匹敵するぐらい事業の柱になります。
ただ、勘違いしないでほしいのは、事業にするためとか儲けるためにやっているのではないということ。高齢者に生きがいとか楽しいことを、食品と一緒にお届けするための付加価値事業なんです。お客さんである高齢者の方の息子さん、娘さん、それと孫さんにも読んでほしい。80歳前後の方々がどういう気持ちで、どんなことを考えているのか、ぜひ知ってほしいと思います。
現実から目を背けず、プラス方向への思考で社会課題の解決を
最後にソーシャル・イノベーションについて、事業は結局、政治や社会の枠組みの中でやっていく訳ですから、政治にも社会課題にもいろいろと興味を持ってほしい。世の中は綺麗ごとばかりではないということをぜひ知っておいた方がいい。事業を始めたとき避けて通れませんから。
僕は沖縄や福島をはじめパレスチナ、チェルノブイリなど問題を抱えるところに足を運び、現状を見てきました。最近なら能登半島。地震後の1月6日に「とくし丸」の車両で現地に入り、毎日スーパーで商品を仕入れて5時間6時間かけて被災地に行って配るということを続けました。でも被災地の大規模集会場行くと、全国から送られてきた商品が山のように積まれてあるんです。「この商品、僕らが無料で配ってきますよ」と話を持ちかけても、「それはできない決まりになっています」と。完全に日本の縦割り行政の駄目なところです。4ヶ月経ってやっと復興の兆しも見えて、5ヶ月目からは有料で販売させていただけるようになったんですけれど、今度は7月の豪雨による被災です。一番ダメージを受けた珠洲市の地区に駆けつけたのですが、いたるところで家屋が倒れたまま。地震から半年以上経っても、ほとんど手をつけられてない状態。国は国民を守ってくれないのだ、と心底思いました。福島だってそうです。放射能の問題は、50年や60年じゃない。解決までに100年、200年かかります。チェルノブイリは鉄のドームで囲う工事をしましたが、日本は野ざらし。未だにそのままです。そういう現実があることをきちんと知っておいてほしいと思います。
京セラの創業者である稲盛和夫さんがよく言われていました。「仕事の結果は、能力×やる気×考え方だ」と。勉強していろんな知識を身につけて能力を高める、そういったやる気は0からプラス100。ただ考え方というのは、マイナス100からプラス100まであると。どんなに能力があってやる気があっても、マイナスの考え方や人間というのは、仕事の結果もマイナスなるんです。せっかく能力もあって、やる気もあるなら、プラスの方向で社会にとって良いことをやっていただきたいですね。

【前編】のレポートはここまでです。【後編】では、起業家2名と、京都信用金庫専務理事、琉球大学地域共創科研究科長のパネルディスカッションの模様をお届けします。
2024年10月12日「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」
キックオフセミナー【前編】
[ 2024.12.17 更新 ]
龍谷大学 学長 入澤 崇 開会挨拶
龍谷大学は、いよいよ新しい一歩を踏み出します。この度、沖縄の琉球大学、京都文教大学と連携をして社会課題に向き合い、社会課題を解決しようとする志の高い人材を育成する新しい教育プログラム「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」を開設します。このプログラムは、深刻かつ複雑化する社会課題に向き合い、それを解決しようとする人を育成するという、大学を挙げてのプロジェクトです。
龍谷大学は数年後、京都駅前東側に金融界(京都信用金庫)、産業界(大阪ガス都市開発)とスクラムを組み、社会人そして学生たちが一緒になって、深刻な社会課題を解決する人たちを育成する施設を建設します。今回の養成プログラムに通底するものです。
これからの時代は「共創」です。では何を創るのか。よりよい社会です。これからの未来を創るのは本日来場してくださっているみなさんです。今回の養成プログラムに参加してもらい、充実した学びの時間を過ごしてもらえたらと切に願っております。
ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム 概要説明
龍谷大学政策学研究科長 中森孝文
顕在化していない社会課題から新しい価値を生み出すために
ソーシャル・イノベーションという言葉は、いろんな意味を持って広まっているので、まず私たちが考えるソーシャル・イノベーションとは何かを整理します。
私たちは、タイパやコスパという言葉で表されるような、できるだけ少ない資金で、できるだけ早くできるだけ多くの富を得る経済合理性が好きです。経済合理性を追求すると、新しい技術、新しいモノ、新しい産業、新しい仕組みが生まれ便利になります。しかし便利な社会を追求したが故の弊害も生み出されます。環境への負担もそうですが、給料が良く便利な地域で住みたいという人が増え、過疎問題が生じたり、自分たちさえよければという総取りみたいな考え方になり経済格差を生み出したりします。私たちが取り組む今回のプログラムは、便利で非常に良い社会構造のメリットを享受できない人びとが、直面している困難さを社会課題としてとらえます。そして社会課題から、新しいポテンシャルの芽を見つけて、今までになかったような新しい価値を見出し、社会変革できる力を受講生の皆さんに身につけてもらおうとするものです。
社会課題は行政に解決してもらえばいいという人もいるかもしれません。しかし、社会課題が多様化している今は、一つの自治体や一つの国ではなかなか解決できません。しかも日本は国も自治体も強烈な財政赤字ですから、行政に委ねていては解決できない社会課題が山積しています。そこで必要となるのが、社会課題を多面的な側面から眺め、そこから新しいポテンシャルの芽を見つけ出し、それらを使って今までになかったような新しい価値を生んでいくようなイノベーティブな発想で解決できる人たちなのです。
3大学連携によって多角的な視点と実行力を養う
今回なぜ3大学が連携するに至ったのかというと、多様な社会課題を解決するには、多様な知見はもちろん多様なものの見方が必要だからです。「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」は、ソーシャル・イノベーションとは何かを理解したうえで、3大学から提供される人文・社会科学系科目によって、多様な社会課題に対応できる知識やスキル、多角的な見方など、社会課題解決に必要な基礎的な素養を身につけます。
教育プログラムの仕上げとなるキャップストーン・プログラムは3大学が一緒になり、地域にある社会課題を事例として取り上げて、実際に解決策を考えていきます。沖縄の課題、京都の課題、様々な課題の存在を知り、多面的な視点から課題に向き合い、持続的な解決に向けたビジネスプランなどの計画を立て、必要なプロセスをデザインしていきます。途中、社会課題を提供してくださる関係機関からの評価を受けながら、受講生のアイデアの質を高めていくことで、社会的にインパクトの高い活動をしていく力を身につけていただきたいと思っています。
ソーシャルイノベーターとして社会で認められる制度を確立
もう一つは認証制度です。ヨーロッパはいろいろな国があるため、同じ名称の修士号という学位であっても、国によって学位の能力が違っていることもあります。そこでヨーロッパのどこに行っても、その力を持っているということを証明する制度(EQF)を設けています。それを応用し、琉球大学を修了した人も京都文教大学を修了した人も龍谷大学を修了した人も、修士号という学位だけでなく、ソーシャル・イノベーションの人材だと証明できる資格をつくろうと考えています。
昨今は、企業や団体などに所属する社員や職員をはじめ、社会人の学び直しの機運が高まっているので、オンラインの科目も充実させ、夜間や土曜日にも受講できるような体制をつくってまいります。龍谷大学政策研究科では1年で修士号を取得できる制度もあります。ぜひ、さまざまな知識やスキル、多面的な見方といった知見を大学院で習得していただき、それらの知見を用いて社会課題の解決につなげていっていただきたいと思います。
講演 「社会課題解決に向けた新たな価値創造」
株式会社とくし丸 取締役 住友達也氏
買い物難民という社会課題を解決するビジネスモデルを構築
僕は23歳で資金も経験もキャリアも人脈も何にもないからところから出版社を立ち上げ、経常利益毎年10%以上という会社に育て上げました。1000社起業して残るのは数社というなかで、なぜ生き残れたのかというと、真面目に一生懸命頑張るのは当たり前として、雑誌や広告業界などメディアが非常に伸びていた時代に乗っかったんだろうと思います。46歳のとき、得意でなかった組織運営や経営は人に任せて、出版社を退職し、その後の人生を楽しんでいました。移動スーパーを始めようと思ったのは、高齢の母が「買い物難民」になっているという事実に直面したからです。高齢者人口は増える一方なのに、それを支える若い世代は減っていく。今後、困った高齢者の数は、ますます増えていくことになる。この市場は伸びると思いました。
移動スーパー「とくし丸」の販売員はすべて個人事業主です。僕らはプロデューサー的な立場で「とくし丸」というブランドをつくり、地域のスーパーと契約。個人事業主となった販売員はそのスーパーと契約し、商品を借り受けて販売します。
現在、全国140社のスーパーと提携し、1200台の移動スーパー「とくし丸」が走っています。1台あたり150人ぐらいの顧客がいるので、毎日17万人ぐらいのお客さんの元に通っていることになります。
大切なのは困っている人を何とかしたい気持ち
先日「IT企業を成功させました。僕は勝ち組です」という若手の経営者の方が東京から徳島までわざわざ来てくれました。とても賢く、性格も良く、育ちのいい若者なのです。ただ、話を聞いていると、彼らは弱者や困っている人たちのためではなく、自分の半径3キロから5キロの範囲で、綺麗ごとを言いながら、かっこいい事業でお金を集められればいいと思っていると感じたんです。僕はそうはなりたくない。こういった人たちは企業をそこそこ成功させると思うんですけれど、企業というのは5年、10年、30年、その先まで適正な利益を上げながら継続できる仕組みをつくるってことがとても重要なんです。
僕は綺麗ごとではなく、「儲けはお布施」のようなものだと思っています。出版社も「とくし丸」も、お金儲けをしようと思って始めていません。やりたいと思ったことをやって、それが誰かに喜ばれたり、ありがとうって感謝されたりして、その結果としてお布施のようにお金が回ってくる。その仕組みをつくりたいって本気で思っているんです。
食べる楽しみを届けるだけでなく、高齢者の見守りの隊として
「とくし丸」は命を守るための役割も担っています。まず一つは「食」です。「とくし丸」を始めたばかりの頃は、僕自身が販売員となって、高齢者宅を訪問していました。そこで、「移動手段がなく、タクシーに乗って病院に行くときだけしかスーパーに行けない」「足腰が悪いのでご近所さんが1日1回持ってきてくれるお弁当を3回に分けて食べている」など、泣きそうになるような生活をされている方にたくさん出会ったんです。こういう人たちに単なる食べものではなく、新鮮で美味しい食べものを届け、食を楽しむ気持ちを生きる力にしてもらいたいと思っています。
もう一つは「見守り」です。「とくし丸」は対面販売なので、必ず生存確認ができます。実際「いつものおばあちゃんが来ない」と、民生委員さんに電話したら家の中で倒れていたということもあります。こういう話を聞きつけて、ビジネスにしましょう、見守り機器を一緒に販売しましょうと、持ちかけてくる事業所があるんですが、僕はいつもお断りしています。お客さんが調子悪かったり、倒れていたりしていたら、通報するのは人として当たり前であって、自分の大事なお客さんを見守りの代償としてお金に変換するのは違う。多分ビジネスにはなるんでしょうけれども、そこをビジネスにしてはいけない気持ちがとてもある。いつも顔を合わせるおばあちゃんからちょっと調子悪いって聞くと、病院行こうよって言いますよね。ただそれだけ。威張るようなことでもなくて、当たり前なことですから。
生きる楽しみづくりの一環として高齢者向け情報誌を創刊
先ほど申しあげたとおり、僕は会社の経営が得意ではないので、「とくし丸」が軌道に乗ったのを機にM&Aで上場会社に売却しま した。そのタイミングで手を引くつもりだったのですが、「あなた雑誌をつくりたいんでしょう」と、新たな経営元から持ちかけられ、80代前後の方をターゲットにした雑誌『ぐ〜す〜月刊とくし丸』を創刊しました。「とくし丸」の車両と提携スーパーの店頭のみの販売なので、実際のところまだ全然売れていません。でも、『ぐ〜す〜月刊とくし丸』に投稿が掲載された90歳のおばあちゃんから「投稿が載ったのがうれしくて、まだしばらく頑張って生きようと思います」という編集者冥利に尽きるお便りが届いたんです。こんなに喜んでくれる、生きがいになるっていう、お便りがもらえる雑誌の編集者ってなんて、幸せなんだろうって。
創刊から1年間で数千万の赤字のですが、この雑誌は高齢者たちに必ず爆発的にヒットします。1冊280円。この低価格でも5万部以上売れると儲かるんです。まずは「毎回楽しみに読んでいます」という5万人以上の人たちを僕はつくっていく。さらにそれが10万20万人になれば、本業の移動スーパーに匹敵するぐらい事業の柱になります。
ただ、勘違いしないでほしいのは、事業にするためとか儲けるためにやっているのではないということ。高齢者に生きがいとか楽しいことを、食品と一緒にお届けするための付加価値事業なんです。お客さんである高齢者の方の息子さん、娘さん、それと孫さんにも読んでほしい。80歳前後の方々がどういう気持ちで、どんなことを考えているのか、ぜひ知ってほしいと思います。
現実から目を背けず、プラス方向への思考で社会課題の解決を
最後にソーシャル・イノベーションについて、事業は結局、政治や社会の枠組みの中でやっていく訳ですから、政治にも社会課題にもいろいろと興味を持ってほしい。世の中は綺麗ごとばかりではないということをぜひ知っておいた方がいい。事業を始めたとき避けて通れませんから。
僕は沖縄や福島をはじめパレスチナ、チェルノブイリなど問題を抱えるところに足を運び、現状を見てきました。最近なら能登半島。地震後の1月6日に「とくし丸」の車両で現地に入り、毎日スーパーで商品を仕入れて5時間6時間かけて被災地に行って配るということを続けました。でも被災地の大規模集会場行くと、全国から送られてきた商品が山のように積まれてあるんです。「この商品、僕らが無料で配ってきますよ」と話を持ちかけても、「それはできない決まりになっています」と。完全に日本の縦割り行政の駄目なところです。4ヶ月経ってやっと復興の兆しも見えて、5ヶ月目からは有料で販売させていただけるようになったんですけれど、今度は7月の豪雨による被災です。一番ダメージを受けた珠洲市の地区に駆けつけたのですが、いたるところで家屋が倒れたまま。地震から半年以上経っても、ほとんど手をつけられてない状態。国は国民を守ってくれないのだ、と心底思いました。福島だってそうです。放射能の問題は、50年や60年じゃない。解決までに100年、200年かかります。チェルノブイリは鉄のドームで囲う工事をしましたが、日本は野ざらし。未だにそのままです。そういう現実があることをきちんと知っておいてほしいと思います。
京セラの創業者である稲盛和夫さんがよく言われていました。「仕事の結果は、能力×やる気×考え方だ」と。勉強していろんな知識を身につけて能力を高める、そういったやる気は0からプラス100。ただ考え方というのは、マイナス100からプラス100まであると。どんなに能力があってやる気があっても、マイナスの考え方や人間というのは、仕事の結果もマイナスなるんです。せっかく能力もあって、やる気もあるなら、プラスの方向で社会にとって良いことをやっていただきたいですね。
【前編】のレポートはここまでです。【後編】では、起業家2名と、京都信用金庫専務理事、琉球大学地域共創科研究科長のパネルディスカッションの模様をお届けします。