
3大学がワンチームで実社会の課題解決に挑むプログラムの重点演習
2025年7月5日(土)、琉球大学附属図書館 ラーニング・コモンズにて、「ソーシャル・イノベーション実践演習」中間発表会が開催されました。
【前編】に続き、4つのチームが取り組む地域の課題の内容と担当教官のコメント、さらにチームでのプロジェクトの進め方、中間発表を終えての手応えや最終発表会に向けての改善点などをメンバーの声を交えてお伝えします。(順番は中間発表会当日通り)
「学びの多様性と教育をめぐる課題 ~発達障がい者のキャリア形成に関する現状と課題、支援の「つながり」について~」(学びの多様性班)
メンバー/成松正樹(龍谷大学大学院)、金田佳宏、山入端力也(琉球大学大学院)、横山温子(京都文教大学大学院)

〈テーマ概要〉
発達障がいの子どもたちの教育とキャリア形成について。近年、発達障がい者のキャリア形成支援に対する社会的関心が高まっているが、実際には本人と家族が望む進路を選択できていないケースは少なくない。発達障がいや発達特性のある子どもが自分の個性と可能性を十分発揮でき、希望する将来を叶えられる教育と社会システムを考える。
〈研究・調査〉
人まず発達障がいについて調査。先天的な脳機能に由来すると医学的に診断されている人に加えて、発達特性という診断には至らない、いわゆるグレーゾーンの人も多い上、支援制度から漏れている事実を把握。発達障がい児童の教育・支援活動を行う株式会社サイクロス「あすはな先生」や、学校現場で活躍する臨床心理士などへのインタビューを行うなど現場の声を聞き、発達障がいが社会に理解されていない、専門的な教育機関や支援策の情報がではなく、受け入れ体制も万全ではないといった課題を分析。
〈課題解決に向けて〉
発達障がいや発達特性のある子どもと保護者、教育・支援機関、そして就労可能な企業や組織を「つなぐ」社会的システムの構築が必至。国立特別支援教育総合研究所をはじめとする行政の専門機関などへのインタビューも行い、データを収集・分析していく。
●担当教官/京都文教大学臨床心理学部 大橋良枝教授

発達障がいの方と共に生きるためには、社会構造や社会的価値の問題、日本の教育制度の問題など大変幅広く、ここまで辿り着くのも大変だったでしょう。その中で、実際に支援などに関わる方へのインタビューから分析したことはメンバーの皆さんの理解を深める上で効果的な方法だったと思います。一方で、プロジェクトの焦点がキャリア形成そのものなのか、教育におけるキャリア形成なのかを明確にする必要があります。児童教育期、高等教育期と、成長段階によっても方法が異なるためです。また、発達障がいのある方と共に学び、生きることは双方にメリットがあるとの考えが北欧をはじめ、世界的に広まりつつありますが、日本の「分ける教育」に浸透していくのかを推し量ることも必要ではないでしょうか。
●学びの多様性班メンバーコメント
臨床心理、児童福祉を専門とするメンバーの研究内容を活かしつつ、専門やキャリアの異なるメンバーのさまざまな知見と視点からテーマを深掘りしています。大橋先生に指摘いただいた概念が広いテーマのために、焦点化する場所によって、立案する課題解決策の色が変化することを改めて感じました。どこに焦点を合わせゴールへと運んでいくかについては、一本の糸の単線型とは異なり、いくつかの糸が交じり合うロープのような複線型の概念となって、子どもたちや保護者、支援者、教育・就労機関をつないでいく仕組み、まなざし、社会の有り様を探っていきたいです。
最終発表会に向けては、ここまで以上に現場で携わる方の思いや課題感、困り感に耳を傾け、現場の等身大の課題を考察。それを解決するにはどのような取り組みが有効なのか。一定の示唆を与えるだけではなく、実際に課題解決策として実行いただけるような施策を提示できればと考えています。
「障がい者雇用の現況と地域資源の発掘」(障がい者雇用チーム)
メンバー/西口高貴 、林リエ (龍谷大学大学院)、安里恵美 (琉球大学大学院)、橘今日子 (京都文教大学大学院)

〈テーマ概要〉
障がい者の働き方、働く場の課題解決をめざす。近年、障がい者雇用が進んでいるが、非正規雇用などの不安定な雇用・労働条件のもとで、働く人が少なくない。これらの現状は、資本主義的合理性にあると考えられることから、就労・労働だけでなく、さまざまな場面で障がい者が排除される社会構造そのものを変えるためのアイデアを見い出す。
〈研究・調査〉
琉球大学大学院から提案されたテーマだったこともあり、沖縄県北中城村でバニラビーンズの栽培において障がい者を雇用する事業をスタートアップし、2024年10月の「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム キックオフセミナー」に登壇したソルファコミュニティ代表・玉城卓氏に協力を仰ぎ、取り組みを現地調査。玉城氏の事業がソーシャル・イノベーションの成功例となったのは、農福連携だけでなく、希少性の高いバニラビーンズの収益によって事業が成り立ち、雇用が継続されていること。地域の人たちと障がい者との交流や協働が地域活性化にもつながっていると分析。
〈課題解決に向けて〉
新たな障がい者雇用を生み出すには、地域の物的・人的資源を活かす、特に「人のつながり」を形成することが重要。玉城氏の農園で働く人たち、地域の人たちに加えて、農園のバニラビーンズを使う大手パティスリーへのインタビューも行い、「人のつながり」でソーシャル・イノベーションを起こすアイデアを創出していく。
●ソルファコミュニティ代表 玉城卓氏コメント

私たちは「福祉事業らしくない施設」であり、就労支援のスタッフはあえて福祉の未経験者を雇用しています。障がい者雇用という社会課題解決を目標に掲げていますが、私にとっては障がい者もスタッフも一緒に働く仲間であり、ケアとか支援とかいった感覚はありません。障がい者雇用チームの皆さんは「人とのつながり」に焦点を当ててくださっていますが、確かに私たちが始めたバニラビーンズの栽培も人とのつながりによって広がっています。大手パティスリーとの連携やメディアからの取材、セミナーの開催なども人とのつながりによって実現しました。今後はメンバーの皆さんのアイデアも参考に、農業でしっかり売上を上げ、福祉で働く人をステップアップさせることが重要だと考えています。また、農園の障がい者やスタッフが新規就農することも目標であり理想です。農業という仕事は、作業を細分化しやすく、障がいがあっても働くことができるので、福祉との親和性が高いと思います。植物を育てるのも、人を育てるのも、そして社会課題を解決するのも同じ。よく見て、よく手をかけて、育つ環境を耕していくことが大切ではないでしょうか。
●障がい者雇用チームメンバーコメント
3大学の混成チームであり、社会人、大学院生とキャリアも立場も異なるのですが、オンラインやLINEで密にコミュニケーションを図り、プロジェクトを進めています。それぞれの大学院での講義が終わった後に琉球大学大学院の先生も参加してくださって、遅くまでディスカッションを重ねることもしばしば。プロジェクトやソーシャル・イノベーションに関するさまざまな意見を聞き、学べることは本当に貴重で感謝しています。
玉城さんの協力も人とのつながり=3大学の連携によるものです。障がい者の雇用と地域の理解には大変な面もあると思いますが、楽しく、軽やかに取り組んでおられる玉城さんにならって、私たちも「楽しい」を大切にプロジェクトを進めています。
10月に開かれる日本ソーシャル・イノベーション学会(※)第7回年次大会でこのプロジェクトについて発表するのですが、そこでは農園や関係者へのインタビューによって語られた「物語」を通して、解決策を見い出す「ナラティブアプローチ」という手法での考察とプレゼンを予定しています。
※日本ソーシャル・イノベーション学会
概要:高等教育機関によるSI実践養成の実践として、3大学連携SI人材養成プログラムの取り組み紹介と、PBL型キャップストーン科目受講生による事業提案を実施。
3大学のリソースを大いに活用して、イノベーティブな風を!
持ち時間20分という短さながら、4つのチームはそれぞれ熱のこもったプレゼンテーションを行い、教職員をはじめ、参加者にもプロジェクトへの思いや今後の進行への意欲が伝わったようです。
最後に3大学の先生から講評がありました。
●琉球大学大学院地域共創研究科 本村 真研究科長

立場が異なるメンバーがチーム一丸となり、共に課題解決のプロジェクトに取り組むことは、皆さんが「ソーシャルイノベーションデザイナー」として社会で活躍する時と同じです。今回、中間発表会で受けたアドバイスも参考に、フィールドに出て現状をこの目で見て把握したり、3大学のリソースを活かして考察したりして、力を合わせて最終発表会に挑んでください。私はその日が今から楽しみです。
●京都文教大学大学院臨床心理学研究科 濱野 清志研究科長

ソーシャル・イノベーションは当たり前の概念や情報から聞こえない声、気づいていない事柄を発見していくことから始まりますよね。そこで、臨床心理学の専門家として、4つのテーマを「人」に見立ててコメントしたいと思います。まず、老朽化した団地は今の状態をどのように思っているのでしょうか。京都では洛中・洛外といって区別されていますが、洛外はどう感じているのでしょうか。団地も洛外も嘆いているかもしれませんね。続いて、京町家も同じように取り壊されること、保存されることをどう思っているのか。人に住み続けてほしいのか、観光客などに見てほしいのかも気になるところです。また、教育には公の教育と私の教育があるのですが、一定に並べることは良しなのか。そして、労働、人が働くということはそもそも何なのでしょうか。次元の違う視点から課題を見つめ、考えることもプロジェクトのブラッシュアップにつながると思います。
●龍谷大学政策学部 中森孝文政策学部長
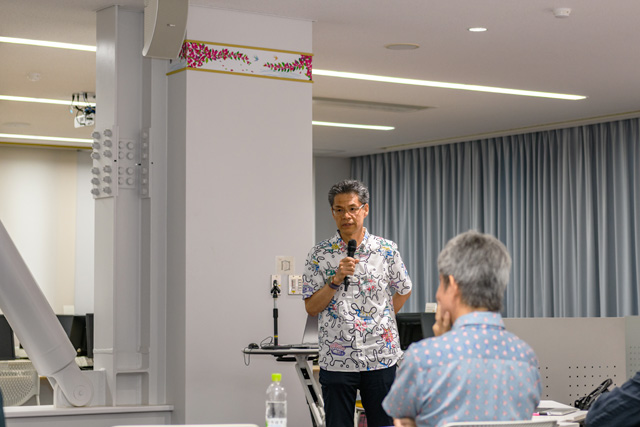
本日、皆さんがプレゼンテーションする姿を見て、私は安心しています。「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」の準備段階では「本当に受講者が集まるだろうか」と心配していたからです。三人寄れば文殊の知恵といいますが、本村先生、濱野先生をはじめ、3大学がワンチームとなってプログラムを創設・始動したからこそ、皆さんが集まり、前向きに学んでくれることにつながったと感謝しています。今回の4つのテーマはどれも一筋縄にはいかないと思います。しかし、困難に向き合えば向き合うほど知恵が生まれます。頭を悩ませ、チームで議論し、力を合わせていく。その過程で得られるものも大きいので、遠慮をせずにどんどんチャレンジしてください。3大学連携というメリットとリソースも活かしましょう。各分野の専門家たちが揃っていますから、アドバイスを求めに行ってください。私たちもそれを待っています。
「ソーシャル・イノベーション実践演習」というこれまでにない新しい形の科目を通じて、全員でイノベーティブな風を吹かしていきましょう。
※最終発表会は2025年12月6日(土)龍谷大学にて開催予定です。
「ソーシャル・イノベーション実践演習」中間発表会 【後編】
[ 2025.10.1 更新 ]
3大学がワンチームで実社会の課題解決に挑むプログラムの重点演習
2025年7月5日(土)、琉球大学附属図書館 ラーニング・コモンズにて、「ソーシャル・イノベーション実践演習」中間発表会が開催されました。
【前編】に続き、4つのチームが取り組む地域の課題の内容と担当教官のコメント、さらにチームでのプロジェクトの進め方、中間発表を終えての手応えや最終発表会に向けての改善点などをメンバーの声を交えてお伝えします。(順番は中間発表会当日通り)
「学びの多様性と教育をめぐる課題 ~発達障がい者のキャリア形成に関する現状と課題、支援の「つながり」について~」(学びの多様性班)
メンバー/成松正樹(龍谷大学大学院)、金田佳宏、山入端力也(琉球大学大学院)、横山温子(京都文教大学大学院)
〈テーマ概要〉
発達障がいの子どもたちの教育とキャリア形成について。近年、発達障がい者のキャリア形成支援に対する社会的関心が高まっているが、実際には本人と家族が望む進路を選択できていないケースは少なくない。発達障がいや発達特性のある子どもが自分の個性と可能性を十分発揮でき、希望する将来を叶えられる教育と社会システムを考える。
〈研究・調査〉
人まず発達障がいについて調査。先天的な脳機能に由来すると医学的に診断されている人に加えて、発達特性という診断には至らない、いわゆるグレーゾーンの人も多い上、支援制度から漏れている事実を把握。発達障がい児童の教育・支援活動を行う株式会社サイクロス「あすはな先生」や、学校現場で活躍する臨床心理士などへのインタビューを行うなど現場の声を聞き、発達障がいが社会に理解されていない、専門的な教育機関や支援策の情報がではなく、受け入れ体制も万全ではないといった課題を分析。
〈課題解決に向けて〉
発達障がいや発達特性のある子どもと保護者、教育・支援機関、そして就労可能な企業や組織を「つなぐ」社会的システムの構築が必至。国立特別支援教育総合研究所をはじめとする行政の専門機関などへのインタビューも行い、データを収集・分析していく。
●担当教官/京都文教大学臨床心理学部 大橋良枝教授
発達障がいの方と共に生きるためには、社会構造や社会的価値の問題、日本の教育制度の問題など大変幅広く、ここまで辿り着くのも大変だったでしょう。その中で、実際に支援などに関わる方へのインタビューから分析したことはメンバーの皆さんの理解を深める上で効果的な方法だったと思います。一方で、プロジェクトの焦点がキャリア形成そのものなのか、教育におけるキャリア形成なのかを明確にする必要があります。児童教育期、高等教育期と、成長段階によっても方法が異なるためです。また、発達障がいのある方と共に学び、生きることは双方にメリットがあるとの考えが北欧をはじめ、世界的に広まりつつありますが、日本の「分ける教育」に浸透していくのかを推し量ることも必要ではないでしょうか。
●学びの多様性班メンバーコメント
臨床心理、児童福祉を専門とするメンバーの研究内容を活かしつつ、専門やキャリアの異なるメンバーのさまざまな知見と視点からテーマを深掘りしています。大橋先生に指摘いただいた概念が広いテーマのために、焦点化する場所によって、立案する課題解決策の色が変化することを改めて感じました。どこに焦点を合わせゴールへと運んでいくかについては、一本の糸の単線型とは異なり、いくつかの糸が交じり合うロープのような複線型の概念となって、子どもたちや保護者、支援者、教育・就労機関をつないでいく仕組み、まなざし、社会の有り様を探っていきたいです。
最終発表会に向けては、ここまで以上に現場で携わる方の思いや課題感、困り感に耳を傾け、現場の等身大の課題を考察。それを解決するにはどのような取り組みが有効なのか。一定の示唆を与えるだけではなく、実際に課題解決策として実行いただけるような施策を提示できればと考えています。
「障がい者雇用の現況と地域資源の発掘」(障がい者雇用チーム)
メンバー/西口高貴 、林リエ (龍谷大学大学院)、安里恵美 (琉球大学大学院)、橘今日子 (京都文教大学大学院)
〈テーマ概要〉
障がい者の働き方、働く場の課題解決をめざす。近年、障がい者雇用が進んでいるが、非正規雇用などの不安定な雇用・労働条件のもとで、働く人が少なくない。これらの現状は、資本主義的合理性にあると考えられることから、就労・労働だけでなく、さまざまな場面で障がい者が排除される社会構造そのものを変えるためのアイデアを見い出す。
〈研究・調査〉
琉球大学大学院から提案されたテーマだったこともあり、沖縄県北中城村でバニラビーンズの栽培において障がい者を雇用する事業をスタートアップし、2024年10月の「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム キックオフセミナー」に登壇したソルファコミュニティ代表・玉城卓氏に協力を仰ぎ、取り組みを現地調査。玉城氏の事業がソーシャル・イノベーションの成功例となったのは、農福連携だけでなく、希少性の高いバニラビーンズの収益によって事業が成り立ち、雇用が継続されていること。地域の人たちと障がい者との交流や協働が地域活性化にもつながっていると分析。
〈課題解決に向けて〉
新たな障がい者雇用を生み出すには、地域の物的・人的資源を活かす、特に「人のつながり」を形成することが重要。玉城氏の農園で働く人たち、地域の人たちに加えて、農園のバニラビーンズを使う大手パティスリーへのインタビューも行い、「人のつながり」でソーシャル・イノベーションを起こすアイデアを創出していく。
●ソルファコミュニティ代表 玉城卓氏コメント
私たちは「福祉事業らしくない施設」であり、就労支援のスタッフはあえて福祉の未経験者を雇用しています。障がい者雇用という社会課題解決を目標に掲げていますが、私にとっては障がい者もスタッフも一緒に働く仲間であり、ケアとか支援とかいった感覚はありません。障がい者雇用チームの皆さんは「人とのつながり」に焦点を当ててくださっていますが、確かに私たちが始めたバニラビーンズの栽培も人とのつながりによって広がっています。大手パティスリーとの連携やメディアからの取材、セミナーの開催なども人とのつながりによって実現しました。今後はメンバーの皆さんのアイデアも参考に、農業でしっかり売上を上げ、福祉で働く人をステップアップさせることが重要だと考えています。また、農園の障がい者やスタッフが新規就農することも目標であり理想です。農業という仕事は、作業を細分化しやすく、障がいがあっても働くことができるので、福祉との親和性が高いと思います。植物を育てるのも、人を育てるのも、そして社会課題を解決するのも同じ。よく見て、よく手をかけて、育つ環境を耕していくことが大切ではないでしょうか。
●障がい者雇用チームメンバーコメント
3大学の混成チームであり、社会人、大学院生とキャリアも立場も異なるのですが、オンラインやLINEで密にコミュニケーションを図り、プロジェクトを進めています。それぞれの大学院での講義が終わった後に琉球大学大学院の先生も参加してくださって、遅くまでディスカッションを重ねることもしばしば。プロジェクトやソーシャル・イノベーションに関するさまざまな意見を聞き、学べることは本当に貴重で感謝しています。
玉城さんの協力も人とのつながり=3大学の連携によるものです。障がい者の雇用と地域の理解には大変な面もあると思いますが、楽しく、軽やかに取り組んでおられる玉城さんにならって、私たちも「楽しい」を大切にプロジェクトを進めています。
10月に開かれる日本ソーシャル・イノベーション学会(※)第7回年次大会でこのプロジェクトについて発表するのですが、そこでは農園や関係者へのインタビューによって語られた「物語」を通して、解決策を見い出す「ナラティブアプローチ」という手法での考察とプレゼンを予定しています。
※日本ソーシャル・イノベーション学会
概要:高等教育機関によるSI実践養成の実践として、3大学連携SI人材養成プログラムの取り組み紹介と、PBL型キャップストーン科目受講生による事業提案を実施。
3大学のリソースを大いに活用して、イノベーティブな風を!
持ち時間20分という短さながら、4つのチームはそれぞれ熱のこもったプレゼンテーションを行い、教職員をはじめ、参加者にもプロジェクトへの思いや今後の進行への意欲が伝わったようです。
最後に3大学の先生から講評がありました。
●琉球大学大学院地域共創研究科 本村 真研究科長
立場が異なるメンバーがチーム一丸となり、共に課題解決のプロジェクトに取り組むことは、皆さんが「ソーシャルイノベーションデザイナー」として社会で活躍する時と同じです。今回、中間発表会で受けたアドバイスも参考に、フィールドに出て現状をこの目で見て把握したり、3大学のリソースを活かして考察したりして、力を合わせて最終発表会に挑んでください。私はその日が今から楽しみです。
●京都文教大学大学院臨床心理学研究科 濱野 清志研究科長
ソーシャル・イノベーションは当たり前の概念や情報から聞こえない声、気づいていない事柄を発見していくことから始まりますよね。そこで、臨床心理学の専門家として、4つのテーマを「人」に見立ててコメントしたいと思います。まず、老朽化した団地は今の状態をどのように思っているのでしょうか。京都では洛中・洛外といって区別されていますが、洛外はどう感じているのでしょうか。団地も洛外も嘆いているかもしれませんね。続いて、京町家も同じように取り壊されること、保存されることをどう思っているのか。人に住み続けてほしいのか、観光客などに見てほしいのかも気になるところです。また、教育には公の教育と私の教育があるのですが、一定に並べることは良しなのか。そして、労働、人が働くということはそもそも何なのでしょうか。次元の違う視点から課題を見つめ、考えることもプロジェクトのブラッシュアップにつながると思います。
●龍谷大学政策学部 中森孝文政策学部長
本日、皆さんがプレゼンテーションする姿を見て、私は安心しています。「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」の準備段階では「本当に受講者が集まるだろうか」と心配していたからです。三人寄れば文殊の知恵といいますが、本村先生、濱野先生をはじめ、3大学がワンチームとなってプログラムを創設・始動したからこそ、皆さんが集まり、前向きに学んでくれることにつながったと感謝しています。今回の4つのテーマはどれも一筋縄にはいかないと思います。しかし、困難に向き合えば向き合うほど知恵が生まれます。頭を悩ませ、チームで議論し、力を合わせていく。その過程で得られるものも大きいので、遠慮をせずにどんどんチャレンジしてください。3大学連携というメリットとリソースも活かしましょう。各分野の専門家たちが揃っていますから、アドバイスを求めに行ってください。私たちもそれを待っています。
「ソーシャル・イノベーション実践演習」というこれまでにない新しい形の科目を通じて、全員でイノベーティブな風を吹かしていきましょう。
※最終発表会は2025年12月6日(土)龍谷大学にて開催予定です。