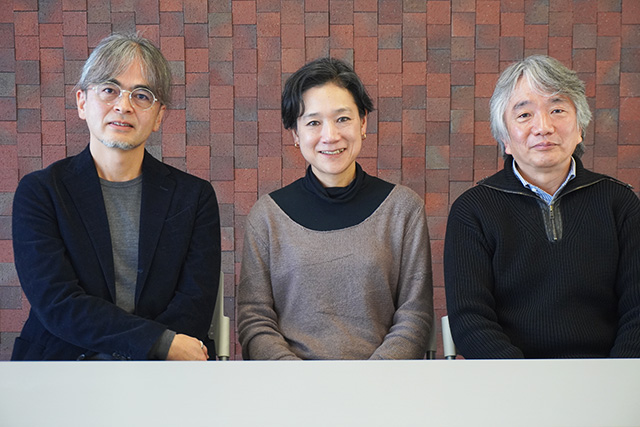
琉球大学大学院地域共創研究科、京都文教大学大学院臨床心理学研究科、そして龍谷大学政策学研究科の3大学連携の意義、連携の強みを教えてください。
大石:社会課題は、地域で全然違うんですよ。 例えば同じ貧困問題でも沖縄と京都ではその背景や歴史が違うから解決の方法も違ってきます。京都にある龍谷大学と京都文教大学、そして沖縄の琉球大学がお互いの地域を学ぶことで、また視点が変わった捉え方というか、俯瞰的に捉えることができるようになります。翻ると、京都と沖縄の共通項もみえてくる。そこが連携の魅力だと思います。
内田:イノベーティブな変化が起こったときのハレーションというか抵抗も、京都と沖縄ではその現れ方が違ってきますからね。ゴールとしてはすごくいいものでも、地域を理解した上で考えていかないと途中の段階でいろんな問題が起こってしまって結局うまくいかなくなってしまう。社会問題って本当に複雑なんです。本学の政策学研究科も、スタッフや教授が揃ってはいるわけですけれども、複雑な社会課題に対応するには1研究科だけではどうしても足りない。でも今回のプログラムは、3大学がオンラインの力を借りて相互にいろんな学問的なサービスを提供できる。院生は三つの学問領域から興味がある科目を自由に選び、いろんな分野の先生から学ぶことができる。これってものすごいメリットだと思います。
的場:とくに京都文教大学が入っているのが面白いですよね。プログラム修了時に獲得することが期待される能力としてセルフコントロールっていう言葉を入れているんですが、人とのコミュニケーションだけでなく、自分自身をどう考えるかっていうところも含め、専門的な知識でサポートしていただけるっていうのはとてもありがたい。
大石:臨床心理って個人の中に出てくる問題ですけれども、社会構造や企業構造などから発生していることが多いですから、広い理解は重要になってきますよね。
内田:京都文教大学の濱野先生がおっしゃっていたんですが、例えばコミュニケーションって、自分が思っていることを伝えるということだけでなく、相手がどう受け止めるのかとかいうことも重要なんですよね。特にイノベーションを起こすとなると先ほども言ったとおり、抵抗もある。我々としては、どのようにイノベーションを起こしていけばいいのかを心理的な観点から学べることに期待しています。あと心理学を勉強した方々にとっては、ソーシャル・イノベーションの文脈の中で、自分たちのスキルや知識を使えるのは、新たなキャリアを考える上で非常に重要なことになってくると思います。
共通基礎科目ついて「社会構造・社会課題」、「起業・マネジメント」、「イノベーション・変革」、「全体(ソーシャル・イノベーション全般)」 の4つの領域に分類されておられますが、具体的にはどのような学びになるのでしょうか。
内田:まずソーシャル・イノベーションというものがどういうものなのか、きちんと理解するための基礎を多くの先生の講義を受けて、きちんと勉強していただきます。
的場:「社会構造・社会課題」、「起業・マネジメント」、「イノベーション・変革」、「包括的視点」の分野から最低1科目(2ポイント)ずつ取り、自身の専門や関心に合わせてプラスもう1科目いずれかの科目群の中から取れば基礎科目群の学びは完成します。
大石:修士を取ろうと思ったらもっといっぱい取らないといけないですが (笑)
内田:例として、ビジネススクールなどでも企業の戦略や資金調達などのビジネスプランを考え、評価するというのはやっていると思うんですが、このプログラムの「起業・マネジメント」では、NPOのマネジメントをどうしていったらいいのといった知識も提供されます。
的場:ヨーロッパでは公務員とか公的な組織にこそ、イノベーションが必要と考えられていて、既存のビジネススクールのカリキュラムをベースに、公共セクターに対応した教育プログラムを開発しているところもあります。われわれのプログラムは、企業セクターだけでなく、本研究科が元々強い公共セクター関連の教育とビジネス的な要素を組み合わせて、公務員やNPOなどあらゆるセクターのイノベーションを考えられるところもひとつの強みになっています。

キャップストーン科目の内容について、1年間かけて、チームで現場巡検や実習・演習を行い、ソーシャル・イノベーションの実践的な提案を行う、チームは所属大学院にかかわらず、受講生どうしで共通する関心テーマに則して編成するとありますが、具体的な進め方、内容などを教えてください。
内田:我々の最終ゴールはソーシャル・イノベーションを起こせる人材の育成なので、フィールドワークをきちんとして、実践的なトレーニングを行うことが必要です。この実践的なトレーニングというのがキャップストーン科目です。ここでは全ての知識や勉強をもとにして、現実の問題に応用して考えていきます。課題は行政、NPO、地域の金融機関、あとは地域の課題解決をやりたいといった企業など、本学の教育パートナーの方々に出していただきます。
的場:その中から最も自分の関心の高いものや、自分の仕事に近いものを選んで課題をやってもらうという形になるんですよね。
内田:そうです。あとは大学の垣根なく、オンラインを駆使しながらグループで課題を解決していきます。流れとしては院生に具体的な社会課題を根底からきっちりと分析し、どういう社会構造でこういう問題が生まれているのか、それに対してどんな解決をするのかをしっかりと考えていただく。それを協力いただいた企業や団体に報告し、評価をいただいた後、さらに持ち帰ってブラッシュアップし、完成版を仕上げる。教育のプログラムとしては、内容をまとめるだけでなく、振り返りみたいなこともきちんとやっていただいて最終的にレポートを出すという形になります。
我々はいろんな観点からコメントを入れたりして、わざと議論を引っかきまわすことをしますが、そのことをヒントとして自分たちでさらに考えて、この社会課題の解決策はこれがベストだ、と結論に導いていただきます。
大石:これと同時に修士論文も書かなきゃいけないので、ちょっと大変ですが、キャップストーンで取り組んだ課題を修士論文のテーマにすることもできますので、研究をより深化させることができると思います。
実践できる場が用意されていると言うことですね。受講された方について、将来どのような場で活躍することを期待されますか。
的場:本プログラムは、いろんな場で活躍される方々に広く対応できるものなっていると考えています。フォーカスがないのはどうかとは思ったりしますが、ただ私個人としては新たに起業を考える方ももちろんですが、むしろ今置かれている状況をしっかりと見据えて、そこから何か新しい違ったものを生み出せる人になってほしい。オルタナティブという言葉を日本語にすると難しいんですが、今までとは違った形で物事を考えられる。もしそこでパワーがあるんだったら、そこから自分の職場環境や組織の選択を変えていける。公務員としてイノベーションを考えるとか、今いるところで新しい変革を生み出せるような人になってほしいなと。これはプログラム全体っていうよりも、私の個人的な希望です。
大石:私も今そこにいる人と世の中をどう変えていくかという視点で持ちつつ、より良い環境を作っていくように、自ら活動をできるような人材になっていただきたいなと思います。もう一方でやっぱり自分が気づいていなかった力だったりとかできることに気づいて、やっぱり何か事業化だったりとか活動でもいいんですけども、ネットワークや繋がりの中で新たな活動なり、事業なりを起こす、そういう人もやっぱり出てほしいとも思います。 そして女性の方に多く来てほしい。男女の異なった視点からの認識が必要だと思います。でも女性はまだ社会で平等な地位を得られていないですよね。女性だからできないとか、思ってしまう人も少なくはないのではないでしょうか。だからこそ、このプログラム受講が、女性が自ら何かを作り出して、活動を起こすきっかけになればと思います。

内田:いわゆる社会起業家にならなくてもいろんなところで活躍できるだろうと思います。その中でやはり一番重要なのが、先ほど的場先生がおっしゃったオルタナティブを考えるということ。今のこの社会構造とか社会のあり方って本当はもっとよくすることができるよね、ここに問題があるんだよね、ということを深く考えて別のオルタナティブを出していくということが非常に重要だと思っていて、そういう力を発揮していただきたい。私は中山間地域の再生に関わってきたんですが、根底に都会が上で地方は下だという意識が都市にも中山間地域にもあるんですよ。それは戦後、行政投資がなされ近代産業基盤が築かれた都市とそこから取り残された地方という構図があって、ここに格差が生まれた。でも近代産業にはない自然資源や伝統的な文化という希少性を基にした付加価値をつけていけば格差はなくなる。そして都会の人は地方で安らぎを求め、地方の人は都会の生産性の高いものを受け入れるという対等な相互関係になっていけると思っています。実践しておられる大石先生はいかがですか?
大石:そうですね。さっきの女性の話も一緒で、対等性であったり、自分の価値だったり。そこを再評価し、既存にある権力フローに対して関係性を変えていくことがソーシャル・イノベーションに繋がっていくという気はします。
内田:健全な形の相互依存関係を築くということですね。こういうような認識を作っていくっていうことが多分ソーシャル・イノベーションの一番のポイントなんだろうなと思います。今の社会のメリットを享受できない人たちは、どうしても主従の関係でいうと従の方になってしまう。いや違うんだと、これを正して違う新たな関係を築いていこうと、そういう新たな関係の構築みたいなことに邁進していただける方が出てきたらすごく嬉しいと思っています。
ありがとうございました。
「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」の教育内容と社会人が学ぶ意義について
政策学研究科の3教授が座談会【後編】
[ 2025.3.26 更新 ]
琉球大学大学院地域共創研究科、京都文教大学大学院臨床心理学研究科、そして龍谷大学政策学研究科の3大学連携の意義、連携の強みを教えてください。
大石:社会課題は、地域で全然違うんですよ。 例えば同じ貧困問題でも沖縄と京都ではその背景や歴史が違うから解決の方法も違ってきます。京都にある龍谷大学と京都文教大学、そして沖縄の琉球大学がお互いの地域を学ぶことで、また視点が変わった捉え方というか、俯瞰的に捉えることができるようになります。翻ると、京都と沖縄の共通項もみえてくる。そこが連携の魅力だと思います。
内田:イノベーティブな変化が起こったときのハレーションというか抵抗も、京都と沖縄ではその現れ方が違ってきますからね。ゴールとしてはすごくいいものでも、地域を理解した上で考えていかないと途中の段階でいろんな問題が起こってしまって結局うまくいかなくなってしまう。社会問題って本当に複雑なんです。本学の政策学研究科も、スタッフや教授が揃ってはいるわけですけれども、複雑な社会課題に対応するには1研究科だけではどうしても足りない。でも今回のプログラムは、3大学がオンラインの力を借りて相互にいろんな学問的なサービスを提供できる。院生は三つの学問領域から興味がある科目を自由に選び、いろんな分野の先生から学ぶことができる。これってものすごいメリットだと思います。
的場:とくに京都文教大学が入っているのが面白いですよね。プログラム修了時に獲得することが期待される能力としてセルフコントロールっていう言葉を入れているんですが、人とのコミュニケーションだけでなく、自分自身をどう考えるかっていうところも含め、専門的な知識でサポートしていただけるっていうのはとてもありがたい。
大石:臨床心理って個人の中に出てくる問題ですけれども、社会構造や企業構造などから発生していることが多いですから、広い理解は重要になってきますよね。
内田:京都文教大学の濱野先生がおっしゃっていたんですが、例えばコミュニケーションって、自分が思っていることを伝えるということだけでなく、相手がどう受け止めるのかとかいうことも重要なんですよね。特にイノベーションを起こすとなると先ほども言ったとおり、抵抗もある。我々としては、どのようにイノベーションを起こしていけばいいのかを心理的な観点から学べることに期待しています。あと心理学を勉強した方々にとっては、ソーシャル・イノベーションの文脈の中で、自分たちのスキルや知識を使えるのは、新たなキャリアを考える上で非常に重要なことになってくると思います。
共通基礎科目ついて「社会構造・社会課題」、「起業・マネジメント」、「イノベーション・変革」、「全体(ソーシャル・イノベーション全般)」 の4つの領域に分類されておられますが、具体的にはどのような学びになるのでしょうか。
内田:まずソーシャル・イノベーションというものがどういうものなのか、きちんと理解するための基礎を多くの先生の講義を受けて、きちんと勉強していただきます。
的場:「社会構造・社会課題」、「起業・マネジメント」、「イノベーション・変革」、「包括的視点」の分野から最低1科目(2ポイント)ずつ取り、自身の専門や関心に合わせてプラスもう1科目いずれかの科目群の中から取れば基礎科目群の学びは完成します。
大石:修士を取ろうと思ったらもっといっぱい取らないといけないですが (笑)
内田:例として、ビジネススクールなどでも企業の戦略や資金調達などのビジネスプランを考え、評価するというのはやっていると思うんですが、このプログラムの「起業・マネジメント」では、NPOのマネジメントをどうしていったらいいのといった知識も提供されます。
的場:ヨーロッパでは公務員とか公的な組織にこそ、イノベーションが必要と考えられていて、既存のビジネススクールのカリキュラムをベースに、公共セクターに対応した教育プログラムを開発しているところもあります。われわれのプログラムは、企業セクターだけでなく、本研究科が元々強い公共セクター関連の教育とビジネス的な要素を組み合わせて、公務員やNPOなどあらゆるセクターのイノベーションを考えられるところもひとつの強みになっています。
キャップストーン科目の内容について、1年間かけて、チームで現場巡検や実習・演習を行い、ソーシャル・イノベーションの実践的な提案を行う、チームは所属大学院にかかわらず、受講生どうしで共通する関心テーマに則して編成するとありますが、具体的な進め方、内容などを教えてください。
内田:我々の最終ゴールはソーシャル・イノベーションを起こせる人材の育成なので、フィールドワークをきちんとして、実践的なトレーニングを行うことが必要です。この実践的なトレーニングというのがキャップストーン科目です。ここでは全ての知識や勉強をもとにして、現実の問題に応用して考えていきます。課題は行政、NPO、地域の金融機関、あとは地域の課題解決をやりたいといった企業など、本学の教育パートナーの方々に出していただきます。
的場:その中から最も自分の関心の高いものや、自分の仕事に近いものを選んで課題をやってもらうという形になるんですよね。
内田:そうです。あとは大学の垣根なく、オンラインを駆使しながらグループで課題を解決していきます。流れとしては院生に具体的な社会課題を根底からきっちりと分析し、どういう社会構造でこういう問題が生まれているのか、それに対してどんな解決をするのかをしっかりと考えていただく。それを協力いただいた企業や団体に報告し、評価をいただいた後、さらに持ち帰ってブラッシュアップし、完成版を仕上げる。教育のプログラムとしては、内容をまとめるだけでなく、振り返りみたいなこともきちんとやっていただいて最終的にレポートを出すという形になります。
我々はいろんな観点からコメントを入れたりして、わざと議論を引っかきまわすことをしますが、そのことをヒントとして自分たちでさらに考えて、この社会課題の解決策はこれがベストだ、と結論に導いていただきます。
大石:これと同時に修士論文も書かなきゃいけないので、ちょっと大変ですが、キャップストーンで取り組んだ課題を修士論文のテーマにすることもできますので、研究をより深化させることができると思います。
実践できる場が用意されていると言うことですね。受講された方について、将来どのような場で活躍することを期待されますか。
的場:本プログラムは、いろんな場で活躍される方々に広く対応できるものなっていると考えています。フォーカスがないのはどうかとは思ったりしますが、ただ私個人としては新たに起業を考える方ももちろんですが、むしろ今置かれている状況をしっかりと見据えて、そこから何か新しい違ったものを生み出せる人になってほしい。オルタナティブという言葉を日本語にすると難しいんですが、今までとは違った形で物事を考えられる。もしそこでパワーがあるんだったら、そこから自分の職場環境や組織の選択を変えていける。公務員としてイノベーションを考えるとか、今いるところで新しい変革を生み出せるような人になってほしいなと。これはプログラム全体っていうよりも、私の個人的な希望です。
大石:私も今そこにいる人と世の中をどう変えていくかという視点で持ちつつ、より良い環境を作っていくように、自ら活動をできるような人材になっていただきたいなと思います。もう一方でやっぱり自分が気づいていなかった力だったりとかできることに気づいて、やっぱり何か事業化だったりとか活動でもいいんですけども、ネットワークや繋がりの中で新たな活動なり、事業なりを起こす、そういう人もやっぱり出てほしいとも思います。 そして女性の方に多く来てほしい。男女の異なった視点からの認識が必要だと思います。でも女性はまだ社会で平等な地位を得られていないですよね。女性だからできないとか、思ってしまう人も少なくはないのではないでしょうか。だからこそ、このプログラム受講が、女性が自ら何かを作り出して、活動を起こすきっかけになればと思います。
内田:いわゆる社会起業家にならなくてもいろんなところで活躍できるだろうと思います。その中でやはり一番重要なのが、先ほど的場先生がおっしゃったオルタナティブを考えるということ。今のこの社会構造とか社会のあり方って本当はもっとよくすることができるよね、ここに問題があるんだよね、ということを深く考えて別のオルタナティブを出していくということが非常に重要だと思っていて、そういう力を発揮していただきたい。私は中山間地域の再生に関わってきたんですが、根底に都会が上で地方は下だという意識が都市にも中山間地域にもあるんですよ。それは戦後、行政投資がなされ近代産業基盤が築かれた都市とそこから取り残された地方という構図があって、ここに格差が生まれた。でも近代産業にはない自然資源や伝統的な文化という希少性を基にした付加価値をつけていけば格差はなくなる。そして都会の人は地方で安らぎを求め、地方の人は都会の生産性の高いものを受け入れるという対等な相互関係になっていけると思っています。実践しておられる大石先生はいかがですか?
大石:そうですね。さっきの女性の話も一緒で、対等性であったり、自分の価値だったり。そこを再評価し、既存にある権力フローに対して関係性を変えていくことがソーシャル・イノベーションに繋がっていくという気はします。
内田:健全な形の相互依存関係を築くということですね。こういうような認識を作っていくっていうことが多分ソーシャル・イノベーションの一番のポイントなんだろうなと思います。今の社会のメリットを享受できない人たちは、どうしても主従の関係でいうと従の方になってしまう。いや違うんだと、これを正して違う新たな関係を築いていこうと、そういう新たな関係の構築みたいなことに邁進していただける方が出てきたらすごく嬉しいと思っています。
ありがとうございました。