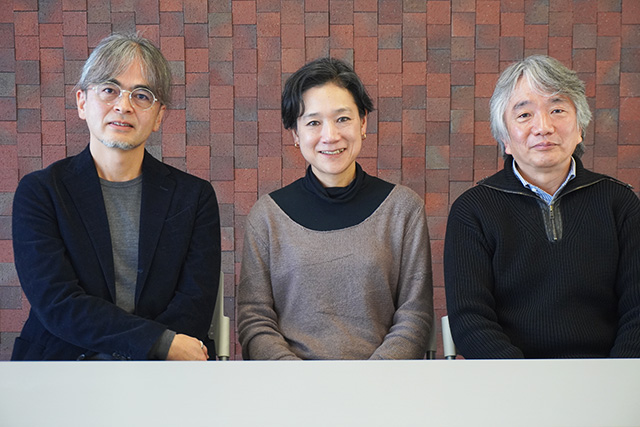
ソーシャル・イノベーションとは具体的にどのようなことなのでしようか。社会課題解決との違いも含め教えてください。
内田:ソーシャル・イノベーションは学問的に統一した定義は未だなく、社会問題、社会課題として何となく認識を持たれているものを解決していくというようなこととして用いられています。我々は3大学として、ソーシャル・イノベーションをきちん定義することが必要だと考え、約1年間かけて議論し、「社会の仕組みに起因する課題に対して、社会構造の根底からの問題理解と経営企画能力との両立をもって、新しい発想や価値を創造し、これらを解決する事業実践を行うこと」としました。
我々の社会はそれなりに便利で、いい社会だとされていますが、その一方でいい暮らしができるメリットを得られない人たちもいます。全員が不満を持っていたら、今のこの社会構造を捨てればいいわけですが、今の社会構造でうまくいっている人たちもいる。そこで必要になるのがイノベーティブな解決なんです。
的場:結果として社会課題解決ではあるんですが、社会構造の枠から出た人たちの捉え方も含め、社会の課題に対するアプローチが違います。
大石:そうですね。既存にあることが、本当にそれでいいのか、疑問を持って物事を捉え、その中の問題に気づく。そして表層的に改善させるのではなく、しっかりその根底を見据えた中でこれまでなかったような方法、新規性があることが、我々が考えるソーシャル・イノベーションです。
内田:具体的に話すと、キックオフセミナーのときに来ていただいた住友 達也さんが始めた移動式スーパー「とくし丸」。今の社会はモータリゼーションに伴って、みんなの利便性を考えて街が作られてきた。大型の施設に車で行ってものを買う。施設を作る側は、固定費はかかるけれども、たくさん人が来ることによって成り立つ。けれど、年を取って、免許を返納しなければならなくなった瞬間に、今まで通りの生活ができなくなる。便利な社会からあふれてしまった人になってしまうんです。それに対して住友さんは、モータリゼーションを逆手に取って、売る人がお客さんのところに行くことにした。既存の社会構造に基づいた解決策では、買い物を代行するという発想になるけれど、そうはしなかった。しかも固定費に関しても一つの会社が全てリスクを背負うのではなく個人事業主というかたちで分散させ、さらにコストも低くすることによって成り立たせた。 これこそ社会のあり方、構造を変える新規性のあるシステムで、ソーシャル・イノベーションといえると思います。

ソーシャル・イノベーション人材養成プログラムは、世間で多く開講されているソーシャルビジネススクールとはどのような点が異なりますか。
内田:全てのソーシャルビジネススクールと言われるところを調べたわけではないんですけども、大半が起業家を講師として集め、その方々の経験や持論、知恵を授かり、新規事業のビジネスプランを構築していくことをメインとしていて、社会構造をしっかりと捉えているというものは少ない。成功者がいろんな経験を語ることには、意味はありますが、我々は社会を理解したうえで議論し、論理的に解決策を導き出していこうと考えています。
的場:ビジネススクールでは、経営手法などは学べると思いますが、内田先生がおっしゃったみたいにこのプログラムは根本的な社会構造とか社会課題みたいなところを広く勉強できるのがいちばんの違いですよね。しかも知りたい、知らなきゃいけないことを自分で選ぶことができる。さらにいろんな学びの要素を踏まえた上で、自分はソーシャル・イノベーションにどのようにアプローチするかをじっくりと考える機会も提供されます。
内田:例えば日本の今の様々な社会課題を考えていたときに、少なくとも戦後の政策がどうなされてきたのかとか。歴史的な流れの中で今の社会構造ができることを知った上で、どうすべきかを考えないと、本当の問題にも気づけないし、おそらく何も生み出せない。そこを勉強してもらえるのかなと思っています。
大石:ソーシャル・イノベーションって、誰かから教えられるものではなく、個人がこれおかしいよね、という気付きから始まって、そこからこれまでにないものが出てくるものですからね。
内田:確かに新規性は、個人の採択に委ねられます。ただ、こうやって考えて、こう捉えていったら、こうなるよねということを、きちんとステップを踏んで学べば、新しいアイデアが生まれやすくなるはずです。
的場:それにこのプログラムは、他の院生や教授陣と議論できる環境があるのも大きいですね。
大石:私としては、ちょっとした社会に対する怒りとか、それがどこから生まれているのか、みたいなことも理解してもらえるのかなと思います。
的場:そうですよね。政策学の分野では、社会や制度に対する何かしらの「怒り」が、先進的な取り組みや革新的な政策を生み出すきっかけになっていることがよくあります。社会への疑問や怒りを持たず、ビジネスの手法だけ学びたい人には、このプログラムは合わないだろうなという気がしますね。
働きながらこのプログラムを学ぶメリットを教えてください。
的場:日本の企業は社員の教育を自社内でやるところも多いですが、ヨーロッパなど欧米諸国は結構外部の組織やプログラムを積極的に活用します。 どんどん外で研修をさせて、修士号や博士号の取得を積極的にサポートする所もあります。企業の中だけだと、コミュニケーションも閉じられたものになりますが、外に出ていくと新たな刺激も多いはずです。特に本学の大学院は公務員もいればNPOの人、企業の人、そして学部から進学した人がいて、かつ留学生も増えているので、本当に多様な人たちと同じところで学べます。自分のセクターと文化が違う人たちと話をしたり、議論したりできるので、すごくいい刺激になるし、視野も開けると思います。
大石:自分の職場がある社会人がここに入ると、絶対元気になると思います。日常の中の何かしらのモヤモヤ感っていうのは多分みんな持ってらっしゃると思うんですよね。でもここで学ぶことで、モヤモヤを解決できるような発想を身につけられる。職場に戻った後も、自分の職場をより面白い形に変えていくような、実際の現場につなげられる力も身につきます。NPOを立ち上げようと思っている方は、来ていただければいろんな繋がりもできますし。非常に魅力的だと思います。
内田:企業の意思決定って割と感覚的なんですよ。この問題はこういう解決しよう、これだったら実現可能性高そうだな、とか。もちろんそこには過去の経験などから見通しを持って判断しているとは思うんですけど、結局、合意が得られればいいんですね。ただグローバル社会でいろんな国との人たちと議論していくとなるとロジックがきちんと伝わるかどうかということが大切になる。自分がなぜこれをいいと思っているのか、さらにいいと思っていることは本当にいいものなのかを考える力をつけられることが、社会人が大学で学ぶ意味なのかなと思います。それに諸外国ではMBAや修士、博士を持っているのが当たり前ですから。
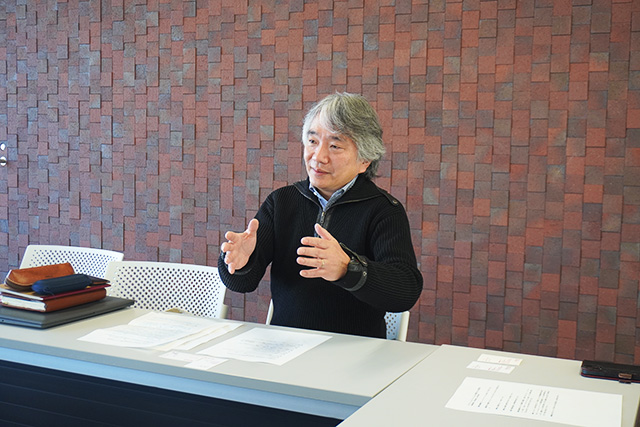
大石:海外では公務員も博士号を持っている人は多いですよね。
的場:自分の組織から一歩外に出ると、MBAや修士、博士など学位や資格を持ってないと自分の能力を証明することが難しいですよね。日本は今まで終身雇用があたりまえだったから、外に対して自分の能力を示すことの必要性があまり認識されてきませんでした。でも、終身雇用の制度が崩壊して、日本でもリスキリングとかリカレントが新たなキーワードとして注目されるようになってきました。このプログラムはSI-Dという資格と修士号の学位の2つを取得することができるので、今働いている職場とは全く違う分野のところで頑張りたいときにも、自分の学びと能力を証明するという点ですごく役に立つと思います。
海外と日本ではそれほど差があるとは驚きました。ただ、社会人が学ぶ際に、実際にやり遂げられるのか、また起業などを考えていないけれど受ける意味があるのか、そう思っておられる方もいらっしゃると思いますが。
的場:元々、本学の大学院は、社会人院生をいっぱい受け入れているので、学びやすい環境が整っています。社会人院生が受講しやすいように、夜間に多くの講義を設定しています。18時35分から6限が始まって7限が終わるのが21時40分。かつ今回は、3大学の連携になるのでオンラインでも授業を提供します。地域公共人材総合研究プログラムは1年間なので、この1年で修士を取るのはものすごくタフなんですが、逆に1年だからモチベーションをキープできるという方もいます。それに卒業生同士の繋がりも強い。このプログラムの修了生は、タフだったけど楽しかった、やって良かったとみなさん言いますよね。
大石:本当に、脱落される方はほとんどいないですね。あんまり青臭いことは言いたくないですけれど、それぞれこれまでやってきたことを1回棚卸しながら、社会貢献だとか、社会を変えていくというところに自分の能力をどう発揮できるかっていうことを考えるのは非常にやりがいがあるし、その後の人生も変わっていくんじゃないかな、と大げさじゃなく思います。
内田:まず、新規事業を立ち上げることだけにフォーカスしているのではないと理解いただきたいですね。行政に残ったままで社会問題を解決したいとか、自分が働いている企業で新規事業を起こしたいとか、漠然とでもいいのでそんな風に思っている人に学んでいただければ。
大石:そうですね、何かやりたいんだけれども、どっから入っていいのかわからない、そういう方にも来ていただきたい。今の自分の仕事に全然リンクしていなかったとしても、このプログラムで学ぶことで、今の仕事の中から何かに繋げていくことができるようになる。自分の殻を突破するきっかけになるはずです。
「ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」の教育内容と社会人が学ぶ意義について
政策学研究科の3教授が座談会【前編】
[ 2025.3.24 更新 ]
ソーシャル・イノベーションとは具体的にどのようなことなのでしようか。社会課題解決との違いも含め教えてください。
内田:ソーシャル・イノベーションは学問的に統一した定義は未だなく、社会問題、社会課題として何となく認識を持たれているものを解決していくというようなこととして用いられています。我々は3大学として、ソーシャル・イノベーションをきちん定義することが必要だと考え、約1年間かけて議論し、「社会の仕組みに起因する課題に対して、社会構造の根底からの問題理解と経営企画能力との両立をもって、新しい発想や価値を創造し、これらを解決する事業実践を行うこと」としました。
我々の社会はそれなりに便利で、いい社会だとされていますが、その一方でいい暮らしができるメリットを得られない人たちもいます。全員が不満を持っていたら、今のこの社会構造を捨てればいいわけですが、今の社会構造でうまくいっている人たちもいる。そこで必要になるのがイノベーティブな解決なんです。
的場:結果として社会課題解決ではあるんですが、社会構造の枠から出た人たちの捉え方も含め、社会の課題に対するアプローチが違います。
大石:そうですね。既存にあることが、本当にそれでいいのか、疑問を持って物事を捉え、その中の問題に気づく。そして表層的に改善させるのではなく、しっかりその根底を見据えた中でこれまでなかったような方法、新規性があることが、我々が考えるソーシャル・イノベーションです。
内田:具体的に話すと、キックオフセミナーのときに来ていただいた住友 達也さんが始めた移動式スーパー「とくし丸」。今の社会はモータリゼーションに伴って、みんなの利便性を考えて街が作られてきた。大型の施設に車で行ってものを買う。施設を作る側は、固定費はかかるけれども、たくさん人が来ることによって成り立つ。けれど、年を取って、免許を返納しなければならなくなった瞬間に、今まで通りの生活ができなくなる。便利な社会からあふれてしまった人になってしまうんです。それに対して住友さんは、モータリゼーションを逆手に取って、売る人がお客さんのところに行くことにした。既存の社会構造に基づいた解決策では、買い物を代行するという発想になるけれど、そうはしなかった。しかも固定費に関しても一つの会社が全てリスクを背負うのではなく個人事業主というかたちで分散させ、さらにコストも低くすることによって成り立たせた。 これこそ社会のあり方、構造を変える新規性のあるシステムで、ソーシャル・イノベーションといえると思います。
ソーシャル・イノベーション人材養成プログラムは、世間で多く開講されているソーシャルビジネススクールとはどのような点が異なりますか。
内田:全てのソーシャルビジネススクールと言われるところを調べたわけではないんですけども、大半が起業家を講師として集め、その方々の経験や持論、知恵を授かり、新規事業のビジネスプランを構築していくことをメインとしていて、社会構造をしっかりと捉えているというものは少ない。成功者がいろんな経験を語ることには、意味はありますが、我々は社会を理解したうえで議論し、論理的に解決策を導き出していこうと考えています。
的場:ビジネススクールでは、経営手法などは学べると思いますが、内田先生がおっしゃったみたいにこのプログラムは根本的な社会構造とか社会課題みたいなところを広く勉強できるのがいちばんの違いですよね。しかも知りたい、知らなきゃいけないことを自分で選ぶことができる。さらにいろんな学びの要素を踏まえた上で、自分はソーシャル・イノベーションにどのようにアプローチするかをじっくりと考える機会も提供されます。
内田:例えば日本の今の様々な社会課題を考えていたときに、少なくとも戦後の政策がどうなされてきたのかとか。歴史的な流れの中で今の社会構造ができることを知った上で、どうすべきかを考えないと、本当の問題にも気づけないし、おそらく何も生み出せない。そこを勉強してもらえるのかなと思っています。
大石:ソーシャル・イノベーションって、誰かから教えられるものではなく、個人がこれおかしいよね、という気付きから始まって、そこからこれまでにないものが出てくるものですからね。
内田:確かに新規性は、個人の採択に委ねられます。ただ、こうやって考えて、こう捉えていったら、こうなるよねということを、きちんとステップを踏んで学べば、新しいアイデアが生まれやすくなるはずです。
的場:それにこのプログラムは、他の院生や教授陣と議論できる環境があるのも大きいですね。
大石:私としては、ちょっとした社会に対する怒りとか、それがどこから生まれているのか、みたいなことも理解してもらえるのかなと思います。
的場:そうですよね。政策学の分野では、社会や制度に対する何かしらの「怒り」が、先進的な取り組みや革新的な政策を生み出すきっかけになっていることがよくあります。社会への疑問や怒りを持たず、ビジネスの手法だけ学びたい人には、このプログラムは合わないだろうなという気がしますね。
働きながらこのプログラムを学ぶメリットを教えてください。
的場:日本の企業は社員の教育を自社内でやるところも多いですが、ヨーロッパなど欧米諸国は結構外部の組織やプログラムを積極的に活用します。 どんどん外で研修をさせて、修士号や博士号の取得を積極的にサポートする所もあります。企業の中だけだと、コミュニケーションも閉じられたものになりますが、外に出ていくと新たな刺激も多いはずです。特に本学の大学院は公務員もいればNPOの人、企業の人、そして学部から進学した人がいて、かつ留学生も増えているので、本当に多様な人たちと同じところで学べます。自分のセクターと文化が違う人たちと話をしたり、議論したりできるので、すごくいい刺激になるし、視野も開けると思います。
大石:自分の職場がある社会人がここに入ると、絶対元気になると思います。日常の中の何かしらのモヤモヤ感っていうのは多分みんな持ってらっしゃると思うんですよね。でもここで学ぶことで、モヤモヤを解決できるような発想を身につけられる。職場に戻った後も、自分の職場をより面白い形に変えていくような、実際の現場につなげられる力も身につきます。NPOを立ち上げようと思っている方は、来ていただければいろんな繋がりもできますし。非常に魅力的だと思います。
内田:企業の意思決定って割と感覚的なんですよ。この問題はこういう解決しよう、これだったら実現可能性高そうだな、とか。もちろんそこには過去の経験などから見通しを持って判断しているとは思うんですけど、結局、合意が得られればいいんですね。ただグローバル社会でいろんな国との人たちと議論していくとなるとロジックがきちんと伝わるかどうかということが大切になる。自分がなぜこれをいいと思っているのか、さらにいいと思っていることは本当にいいものなのかを考える力をつけられることが、社会人が大学で学ぶ意味なのかなと思います。それに諸外国ではMBAや修士、博士を持っているのが当たり前ですから。
大石:海外では公務員も博士号を持っている人は多いですよね。
的場:自分の組織から一歩外に出ると、MBAや修士、博士など学位や資格を持ってないと自分の能力を証明することが難しいですよね。日本は今まで終身雇用があたりまえだったから、外に対して自分の能力を示すことの必要性があまり認識されてきませんでした。でも、終身雇用の制度が崩壊して、日本でもリスキリングとかリカレントが新たなキーワードとして注目されるようになってきました。このプログラムはSI-Dという資格と修士号の学位の2つを取得することができるので、今働いている職場とは全く違う分野のところで頑張りたいときにも、自分の学びと能力を証明するという点ですごく役に立つと思います。
海外と日本ではそれほど差があるとは驚きました。ただ、社会人が学ぶ際に、実際にやり遂げられるのか、また起業などを考えていないけれど受ける意味があるのか、そう思っておられる方もいらっしゃると思いますが。
的場:元々、本学の大学院は、社会人院生をいっぱい受け入れているので、学びやすい環境が整っています。社会人院生が受講しやすいように、夜間に多くの講義を設定しています。18時35分から6限が始まって7限が終わるのが21時40分。かつ今回は、3大学の連携になるのでオンラインでも授業を提供します。地域公共人材総合研究プログラムは1年間なので、この1年で修士を取るのはものすごくタフなんですが、逆に1年だからモチベーションをキープできるという方もいます。それに卒業生同士の繋がりも強い。このプログラムの修了生は、タフだったけど楽しかった、やって良かったとみなさん言いますよね。
大石:本当に、脱落される方はほとんどいないですね。あんまり青臭いことは言いたくないですけれど、それぞれこれまでやってきたことを1回棚卸しながら、社会貢献だとか、社会を変えていくというところに自分の能力をどう発揮できるかっていうことを考えるのは非常にやりがいがあるし、その後の人生も変わっていくんじゃないかな、と大げさじゃなく思います。
内田:まず、新規事業を立ち上げることだけにフォーカスしているのではないと理解いただきたいですね。行政に残ったままで社会問題を解決したいとか、自分が働いている企業で新規事業を起こしたいとか、漠然とでもいいのでそんな風に思っている人に学んでいただければ。
大石:そうですね、何かやりたいんだけれども、どっから入っていいのかわからない、そういう方にも来ていただきたい。今の自分の仕事に全然リンクしていなかったとしても、このプログラムで学ぶことで、今の仕事の中から何かに繋げていくことができるようになる。自分の殻を突破するきっかけになるはずです。